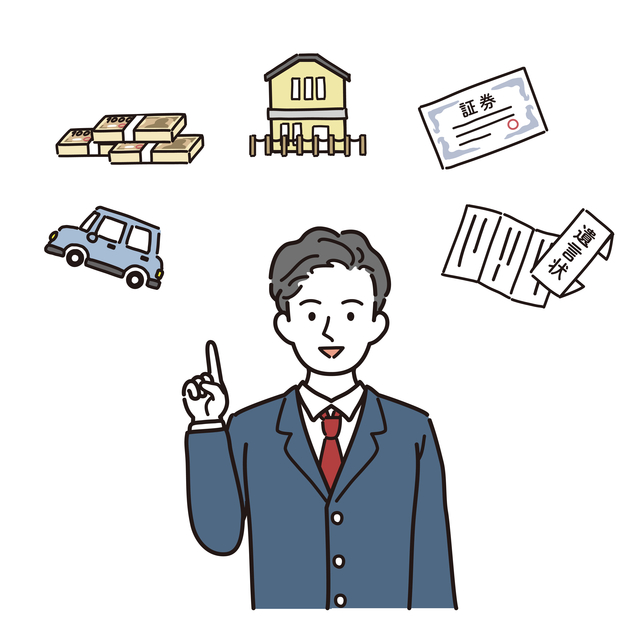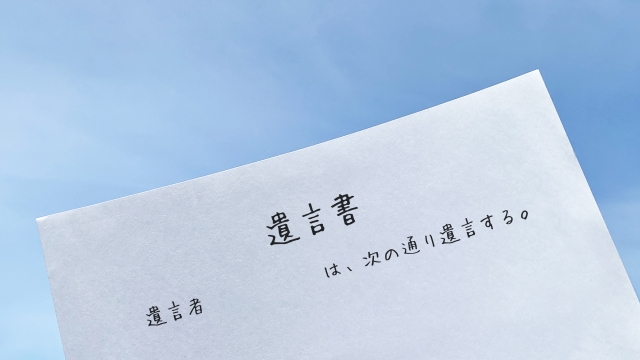
被相続人は、遺言や生前贈与によって、原則として自由に遺産の分け方を決めることができますが、(兄弟姉妹以外の)相続人には遺産のうち一定の割合(遺留分)を確保する権利があります。
遺言や生前贈与により、相続人が遺留分に相当する財産を取得できない場合、遺留分侵害額を請求できます。
以下、請求額の計算方法や請求方法などについて説明します。
なお、遺留分権利者が、相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を受ける必要があります(民法1049条)。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の財産のうち一定の割合が取得できることを相続人に保障する制度です。
例えば、被相続人Aが「すべての遺産をBに相続させる」との遺言を残したとしても、相続人Cは、Bに対して遺留分侵害額に相当する額の金銭を請求することができます。
請求額の計算方法
相続人に対して請求する金額を計算するには、前提として以下の計算が必要となります。
- 遺留分を算定する基礎となる財産
- 遺留分の割合
- 遺留分侵害額
以下、それぞれについて説明します。
遺留分を算定する基礎となる財産
遺留分を算定する基礎となる財産の額は、相続開始の時にあった財産に贈与された財産を加え、債務を引いた額となります(民法1043条1項)。
相続開始の時の財産
まず、相続開始の時に被相続人がもっていた財産が、遺留分を算定するための財産となります。
遺贈された財産は、被相続人が相続開始の時にもっていた財産に含まれます。
贈与された財産
次に、生前、被相続人により贈与された財産が、遺留分を算定する財産となります。
贈与とは、すべての無償による財産の処分を意味します。
例えば、共同相続人間での無償の相続分の譲渡は、譲渡された相続分に財産的価値がない場合を除き、相続分を譲渡した相続人から相続分を譲渡された相続人に対する贈与となります(最高裁平成30年10月19日)。
遺留分を算定する基礎となる財産に含まれるのは、相続人以外に対する贈与と相続人に対する贈与とで異なります。
相続開始前の1年間にされた贈与(1044条1項前段)
贈与契約が相続開始前の1年間に締結された贈与を意味します。
遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与(1044条1項後段)
遺留分権利者に損害を加えるような事実を知っていれば足り、損害を与えるという加害の意図は必要ありません。
また、誰が遺留分権利者であるかを知っている必要もありません。
相続人に対する贈与
相続人に対する贈与のうち、遺留分を算定するための財産となるのは、次のいずれの要件もみたすものに限定されます(民法1044条3項)。
- 婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与(特別受益となる贈与)
- 相続開始前の10年間にされた贈与
債務
最後に、被相続人が負担していた債務(税金も含みます)の額を控除します。
以下、問題となりやすいものについて説明します。
保証債務
保証債務は、主たる債務者が弁済できない状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、その履行による出損を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込みがないような特段の事情がない限り、「債務」には含まれないと考えられます(東京高裁平成8年11月7日)。
したがって、保証債務は、特段の事情がない限り、控除されません。
相続財産に関する費用
相続財産に関する費用(民法885条)とは、遺産の管理費用(固定資産税・地代・家賃、火災保険料、水道料金、電気代、管理費、建物の修繕費用など)や遺言の執行費用のことです。
相続財産に関する費用は、相続開始後に生じた費用であり、被相続人が負担していた債務ではないため、控除されません。
相続財産に関する費用は、各共同相続人がその相続分に応じて負担します。
葬儀費用
葬儀費用は相続開始後に発生した債務であり、喪主が負担すると考えられており、控除されません。
相続税
相続税は相続人の債務であるため、控除されません。
遺留分の割合
各相続人の遺留分の割合は、以下のようになります。
相続人全体に残される遺留分の割合×法定相続分
相続人全体に残される遺留分の割合は、両親のみが相続人の場合は3分の1(民法1042条1項1号)、それ以外の場合は2分の1(民法1042条1項2号)です。
具体的には以下のとおりです。
| 相続人\遺留分 | 配偶者 | 子供 | 両親 |
| 配偶者のみ | 1/2 | ||
| 配偶者と子供 | 1/4 | 1/4 | |
| 配偶者と両親 | 2/6 | 1/6 | |
| 子供のみ | 1/2 | ||
| 両親のみ | 1/3 |
例えば、被相続人Aに妻Bと子供C・Dがいる場合、全財産を妻Bに相続させるという遺言があったときは、次のようになります。
- 相続人全体に残される遺留分の割合=1/2
- 子供B・Cの遺留分=1/2×子供の法定相続分=1/2×(1/2×1/2)=1/8
遺留分侵害額
遺留分侵害額とは、相続人が被相続人の財産から遺留分に相当する財産に不足する額をいいます。
遺留分侵害額は、次の計算式により求めます。
遺留分侵害額
=①遺留分額
-②遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の額
-③遺留分権利者が遺産分割で取得できる額
+④遺留分権利者が負担する債務の額
なお、寄与分(民法904条の2)は家庭裁判所の審判によって有無や額が決まるため、寄与分による修正はしません。
以下、①~④についてそれぞれ説明します。
①遺留分額
遺留分額は、前で説明した遺留分を算定する基礎となる財産の額と遺留分の割合から、次のように求めます。
遺留分額
=遺留分を算定する基礎となる財産の額×遺留分の割合(相続人全体に残される遺留分の割合×法定相続分)
②遺贈・特別受益の額
遺留分権利者が、遺贈・特別受益(903条)を受けていた場合、その価額を遺留分の額から控除します(民法1046条2項1号)。
③遺産分割で取得できる額
遺産分割の対象となる財産がある場合、遺産分割で取得できる財産の価額を遺留分の額から控除します(民法1046条2項2号)。
遺産分割で取得できる財産の額は、具体的な相続分に応じて遺産を配分した時に取得できる財産の価額(遺留分権利者が得た特別受益を考慮し、寄与分は考慮しません。)となります。
④負担する債務の額
被相続人が相続開始時に負担していた債務のうち、相続分に応じた債務の額を加算します(民法1046条2項3号)。
相続分の指定がされた場合、指定された相続分に応じた債務の額を加算します。
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させるとの遺言がされた場合、次のようになります(最高裁平成21年3月24日)。
- 遺留分侵害額の算定にあたり、原則として遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算しない
- 遺留分権利者が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ、これに応じた場合でも、履行した相続債務の額を遺留分の額に加算しない(相続債務をすべて承継した相続人に対して求償できる)
したがって、相続人に対して財産全部を相続させる遺言があった場合、加算される債務の額はないことになります。
寄与分との関係
寄与分は相続人の協議や裁判所の審判によって定められるものであるため、共同相続人からの遺留分侵害額請求に対し、寄与分を主張することによって請求額を減らすことはできないと考えられます(東京高裁平成3年7月30日)。
< 東京高裁平成3年7月30日 >
被控訴人は、…本件不動産につき6割の寄与分があるので、具体的遺留分の計算において、これを考慮すべき旨主張する。
しかしながら、寄与分は、共同相続人間の協議により、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所の審判により定められるものであり、遺留分減殺請求訴訟において、抗弁として主張することは許されないと解するのが相当である。
請求方法
誰に請求できるか
遺留分侵害額を請求できる相手は次のとおりです(民法1046条)。
- 受遺者(特定承継遺言により財産を承継した相続人や相続分の指定を受けた相続人を含みます。)
- 受贈者
- 受遺者・受贈者の承継人
いくら請求できるか
受遺者・受贈者が相続人でない場合
受遺者・受贈者が負担する遺留分侵害額は、受遺者・受贈者が受けた遺贈・贈与の目的の価額が限度となります(民法1047条1項但書)。
受遺者・受贈者が相続人の場合
受遺者・受贈者が負担する遺留分侵害額は、受遺者・受贈者が受けた遺贈・贈与の目的の価額から自らの遺留分の額を控除したが限度となります(民法1047条1項但書)。
裁判所による期限の許与
裁判所は、受遺者・受贈者の請求により、受遺者・受贈者が負担する遺留分侵害額の全部又は一部の支払いについて、相当の期限を許与することができます(民法1047条5項)。
相当の期限を許与するとは、弁済期が変更されることを意味します。
したがって、遺留分侵害額の請求を受けた受遺者・受贈者は、その期限内は支払いを猶予され、遅延損害金を支払う必要もなくなります。
受遺者・受贈者が期限の許与を請求する方法については、遺留分侵害額を請求される裁判の中で主張すれば足りるとの考え(大阪高判平成24年5月31日参照)と期限の許与を請求する訴訟を提起する必要があるとの考え(大阪高判平成14年6月21日参照)があります。
いつまで請求できるか
時効
遺留分侵害額を請求する権利は、次の2つの事項を知った時から、1年間行使しなければ時効によって消滅します(民法1048条前段)。
- 相続の開始(被相続人が死亡したこと)
- 遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと
遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時とは、遺留分権利者が単に被相続人の財産の贈与・遺贈があったことを知るだけでは足りず、遺留分を侵害するものであることも知る必要があると考えられます(最高裁昭和57年11月12日参照)。
そして、被相続人の財産のほとんど全部が贈与され、遺留分権利者がその事実を認識している場合、特段の事情がない限り、その贈与が遺留分を侵害するものであることを知っていたと推認されると考えられます(前掲最高裁昭和57年11月12日参照)。
遺留分侵害額を請求する権利を行使したことにより発生した金銭を請求する権利は、権利を行使できることを知った時から5年間行使しなければ、時効により消滅します(民法166条1項1号)。
除斥期間
遺留侵害額を請求する権利は、時効により消滅するほか、相続開始の時(被相続人の死亡)から10年を経過すると除斥期間により消滅します(民法1048条後段)。
除斥期間とは、権利について法律が定めた存続期間をいい、権利を行使しないままその期間が経過すると、権利が当然に消滅します。
除斥期間は時効と似た制度ですが、援用(民法145条)、更新・完成猶予(民法147条~161条)の制度がないなどの違いがあります。
どのように請求するか
遺留分侵害額を請求するには、遺留分権利者は、受遺者・受贈者に対し、遺留分侵害額を請求する意思表示をします。
遺留分侵害額を請求する意思表示をすることにより、遺留分侵害額に相当する金銭を請求する権利が発生します。
遺留分侵害額を請求する意思表示の際には、具体的な金額まで示す必要はありません。
前で説明したように、遺留分侵害額を請求する権利は時効により消滅するため、意思表示をしたことを明確にしておく必要があります。
そのため、配達証明を付けた内容証明郵便により、遺留分侵害額を請求する意思表示をするのが望ましいです。
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたかということを、郵便局が証明してくれるサービスです。
この点、被相続人の全財産が相続人の一部に遺贈された場合、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求める場合、遺贈の効力を争わずに遺産分割協議の申入れをしたときは、遺産分割協議の申入れに遺留分侵害額を請求する意思表示が含まれていると考えられることもあります(最高裁平成10年6月11日参照)。
しかし、遺産分割と遺留分侵害額の請求とは別の制度ですから、遺産分割協議の申入れに、常に遺留分侵害額を請求する意思表示が含まれていると考えることはできません。
そのため、被相続人の全財産が相続人の一部に遺贈された場合でも、遺留分侵害額を請求する意思表示をしておくことが望ましいです。