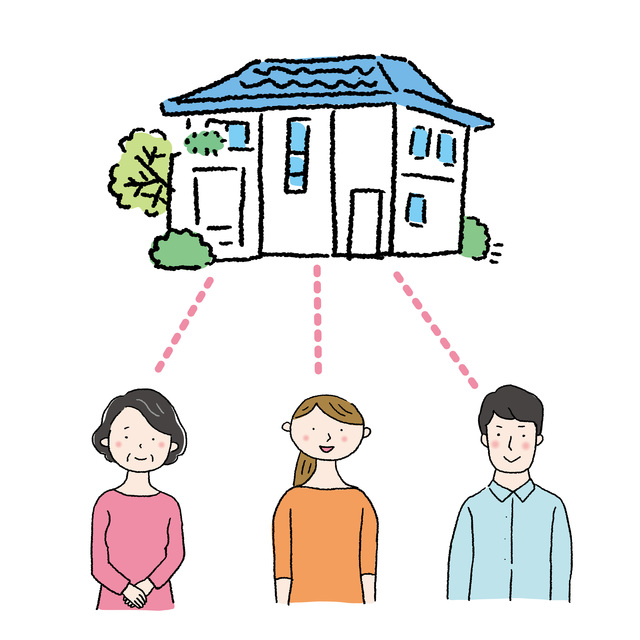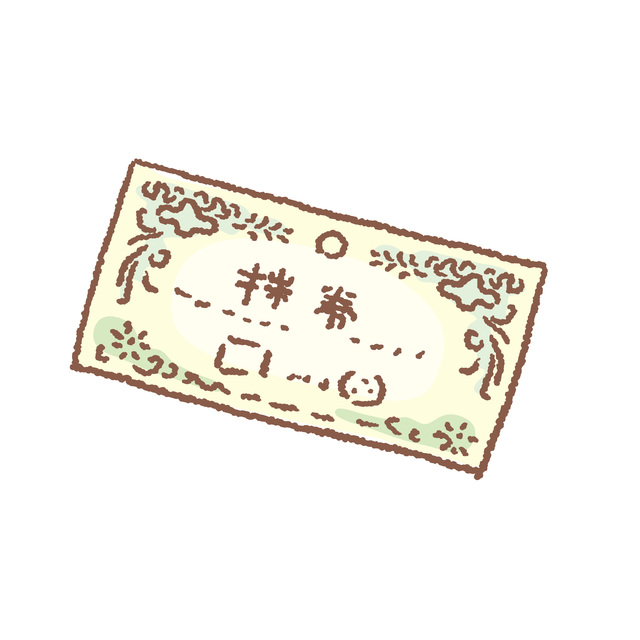特別受益とは
相続人が、被相続人から、次のいずれかの利益を受けた場合、受けた利益の額を考慮して遺産分割を行います(民法903条1項)。
- 遺言により財産を譲り受けた(遺贈)
- 婚姻・養子縁組のために贈与を受けた
- 生計の資本として贈与を受けた
このような遺贈や贈与を特別受益といいます。
遺産分割の際に特別受益を考慮するのは、相続人間の公平を図るためです。
特別受益をどのように考慮するのか
被相続人が死亡した時の財産に、特別受益となる遺贈や贈与を加算したものが遺産とみなされます。
特別受益となる遺贈や贈与を加算することを、特別受益の持戻しといいます。
例えば、相続人が妻・長男・二男の場合において、被相続人の遺産が4000万円あり、生計の資本として長男に1000万円を生前に贈与していたとき、長男への贈与を考慮しないと、妻が2000万円(1/2)、長男が1000万円(1/4)、二男が1000万円(1/4)を取得することになり、長男は贈与と合わせて結果的に2000万円を取得することになります。
しかし、長男への1000万円の生前贈与を考慮すると、遺産は4000万円+1000万円=5000万円あることになり、最終的な取得額は、妻が2500万円、長男が1250万円(既に1000万円を贈与で取得しているので、遺産分割の時点では250万円だけ取得します。)、二男が1250万円となります。
特別受益が相続人の相続分を超える場合、超えた部分を返還する必要はありませんが、遺産から新たに財産を取得することはできません(民法903条2項)。
特別受益となるもの
遺贈
遺贈とは、遺言によって、財産を無償で譲渡することをいいます。
遺贈はすべて特別受益になります(民法903条1項)。
遺贈ではなく「相続させる」という遺言(特定財産承継遺言)も、遺贈と同様に特別受益になると考えられています。
婚姻・養子縁組のための贈与
持参金や支度金
特別受益になると考えられています。
もっとも、少額で、被相続人の資産や生活状況から考えて扶養の一部といえる場合、特別受益にならないと考えられています。
結納金や挙式費用
特別受益にはならないと考えられています。
生計の資本としての贈与
学費
被相続人の生前の経済状況や社会的地位を考えると、相続人を大学等へ通わせたり、留学させるのが扶養の範囲内と思われる場合や、相続人全員が同程度の教育を受けている場合、特別受益にはならないと考えられています。
居住用不動産
居住用不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与は特別受益になると考えられています。
生活費、小遣い、遊興費のための贈与
扶養の範囲内であれば、特別受益にならないと考えられています。
生命保険金
原則として特別受益にならないと考えられています。
もっとも、生命保険金を特別受益として考慮しないと、相続人間の不公平が著しい特別の事情がある場合、特別受益に準じて遺産分割の際に考慮することがあります(最高裁平成16年10月29日)。
具体的には、以下のような裁判例があります。
- 遺産の総額が約6963万円であるのに対して生命保険金の金額が約428万円の場合、生命保険金を考慮しなかった(大阪家裁堺支部平成18年3月22日)
- 遺産の総額が約1億134万円であるのに対して保険金の金額が約1億129万円の場合、生命保険金を考慮した(東京高裁平成17年10月27日)
- 遺産の総額が約8423万円であるのに対して生命保険金の金額が約5154万円の場合、生命保険金を考慮した(名古屋高裁平成18年3月27日)
土地の無償使用
相続人が被相続人の土地の上に建物を建て、土地を無償で使用している場合、土地を無償で使用する権利(使用借権)の評価額が特別受益になると考えられます。
もっとも、相続人に被相続人を扶養する負担がある場合、土地を無償で使用する権利と被相続人を扶養する負担が実質的には対価的な関係にあるといえ、特別受益にはならないと考えられます。
建物の無償使用
相続人が被相続人の建物を無償で使用している場合、建物を無償で使用する権利(使用借権)の評価額は特別受益にならないと考えられます。
相続人以外の特別受益
相続人以外の方が遺贈などを受けたとしても、原則として特別受益にならないと考えられます。
もっとも、名義上は相続人以外への遺贈などでも、実際には相続人への贈与といえる場合、特別受益になると考えられいます。
また、代襲相続の場合、特別受益を考慮することがあります。
代襲相続とは、相続人(被代襲者)が相続開始前に死亡したり、相続人の資格を失ったりした場合、その相続人の直系卑属(代襲相続人)が、相続人に代わって相続することをいいます。
被代襲者が遺贈などを受けた場合
被代襲者の特別受益を代襲相続人が引き継ぐことになると考えられます。
代襲相続人が遺贈などを受けた場合
被代襲者が死亡したり、相続人の資格を失ったりする前に、代襲相続人に特別受益がある場合、代襲相続人の特別受益を考慮しないと考えられます。
これに対し、被代襲者が死亡したり、相続人の資格を失ったりした後に、代襲相続人に特別受益がある場合、代襲相続人の特別受益を考慮すると考えられます。
特別受益の額の評価
特別受益の額は、相続開始の時の価値を評価します。
特別受益に当たる贈与が金銭の場合,贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算します。
相続開始の時の貨幣価値に換算するには、消費者物価指数を参考にして貨幣価値の変動を考慮します。
持戻し免除の意思表示
配偶者に対する居住用建物・敷地以外の遺贈・贈与
被相続人が、特別受益を遺産分割において考慮する必要がないという意思表示をしていた場合、特別受益を考慮せずに(特別受益を遺産に持ち戻さずに)、遺産分割を行います(民法903条3項)。
このように、特別受益を遺産分割において考慮する(持ち戻す)必要がないという被相続人の意思表示を持戻し免除の意思表示といいます。
持戻し免除の意思表示は、遺言などで明らかな意思表示がされていない場合でも、様々な状況から考えて持戻し免除の意思があると推測できるものであれば構いません。
もっとも、遺言などで明らかな意思表示がないと、持戻し免除の意思表示があったかどうかが不明確となり、後に争いの原因となることがなります。
そこで、遺言などに持戻し免除の意思があることを記載することが望ましいです。
なお、遺贈における持戻し免除の意思表示についても、必ずしも遺言による必要はないと考えられます(大阪高裁平成25年7月26日)。
配偶者に対する居住用建物・敷地の遺贈・贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、居住用の建物又はその敷地を、遺贈又は贈与した場合、被相続人は、その遺贈又は贈与について持戻し免除の意思を表示したものと推定されます(民法903条4項)。
この制度は、令和元年7月1日から施行され(附則2条)、施行日前にされた遺贈・贈与には適用されません(附則4条)。
婚姻期間が20年以上の夫婦
居住用建物・敷地の遺贈・贈与の時に婚姻期間が20年以上であることが必要です。
20年の期間に事実婚の期間は含まれません。
居住用建物・敷地
居住用建物・敷地だけでなく、配偶者居住権が遺贈された場合にも、この制度が適用されます(民法1028条3項)。
自宅兼店舗が、居住用建物に該当するかどうかは、不動産の構造・形態、被相続人の遺言の趣旨などによって判断されると考えられます。
例えば、構造上一体となる3階建ての建物の1階で店舗を営業し、2・3階に居住していた場合、居住用建物に該当すると考えられます。
居住用建物・敷地に該当するかどうかは、遺贈・贈与の時点で判断します。
居住用建物・敷地の遺贈・贈与が対象であり、居住用建物・敷地を購入する資金を遺贈・贈与した場合、この制度の適用はありません。
遺贈・贈与
この制度は、遺贈・贈与が対象となっており、「特定の財産を相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)があった場合は、遺産分割方法の指定と考えられているため(最高裁平成3年4月19日)、適用されません。
しかし、遺産の一部について特定財産承継遺言があった場合、あわせて相続分の指定もあったと考えられ、残りの遺産の遺産分割の際には考慮しないことが多く、結果的にはこの制度を適用したのと同様の結果となると考えられます。
推定
被相続人は持戻し免除の意思を表示したと推定されますが、被相続人がこれと異なる意思を表示していた場合、持戻しをすることになります。
特別受益証明書
特別受益証明書とは、被相続人から特別受益を受けた相続人が、相続分のないことを確認した証明書です。
「相続分のないことの証明書」や「相続分不存在証明書」ということもあります。
主に、相続登記の際に利用するもので、共同相続人の特別受益証明書を登記原因証書とすることができることから、簡単に相続登記の手続きをすることができます。
もっとも、以下のようなリスクがあります。
- 相続放棄とは異なり、負債などのマイナスの財産は相続分にしたがって相続する必要がある。
- 実際に生前贈与を受けていなかったり、生前贈与を受けたとしても特別受益にならない場合、本来の相続分を取得できないおそれがある。
後の争いを予防するためには、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成することが望ましいと考えられます。
特別受益が適用される期間
民法改正により、相続開始から10年が経過した後にする遺産分割には、原則として特別受益の規定は適用されないことになりました(改正後民法904条の3柱書本文)。
したがって、相続開始から10年が経過した後には、法定相続分を前提に遺産分割を行うことになります。
特別受益の規定が適用されないことにより、具体的相続分による遺産分割を求める利益がなくなるという効果が生じることになります。
そのため、期間経過後に具体的相続分による分割を求める利益について、不当利得返還請求などを認めることは想定されていません。
もっとも、次のどちらかに該当すれば、相続開始から10年を経過した後でも、特別受益の規定が適用されます(改正後民法904条の3柱書但書)。
- 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
- 相続開始の時から10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、その相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
なお、「やむを得ない事由」とは、客観的な事情から、相続人に遺産分割の申立てをすることを期待することがおよそ期待できない場合をいい、容易には認められないものと考えられます。
改正後の民法は令和3年4月28日から2年以内に施行されることになっており(改正民法附則1条本文)、「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和3年12月14日閣議決定)により、令和5年4月1日に施行されることになりました。
そして、特別受益が適用される期間の制限については、改正民法の施行日前に相続が開始した遺産分割にも遡及して適用されます。
具体的には、次のどちらか遅い時までが特別受益が適用される期限となります(改正民法附則3条)。
- 相続開始の時から10年を経過する時
- 改正民法施行の時から5年を経過する時