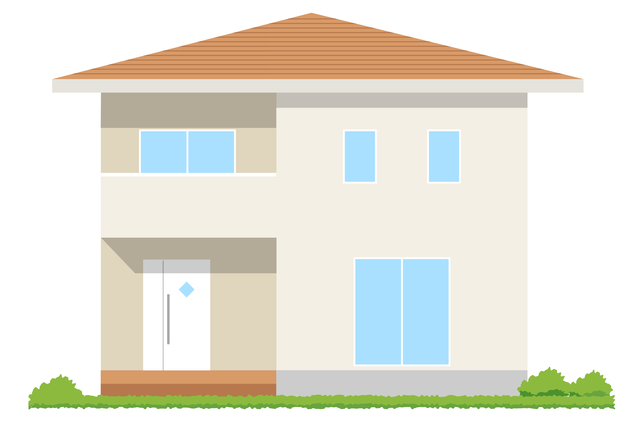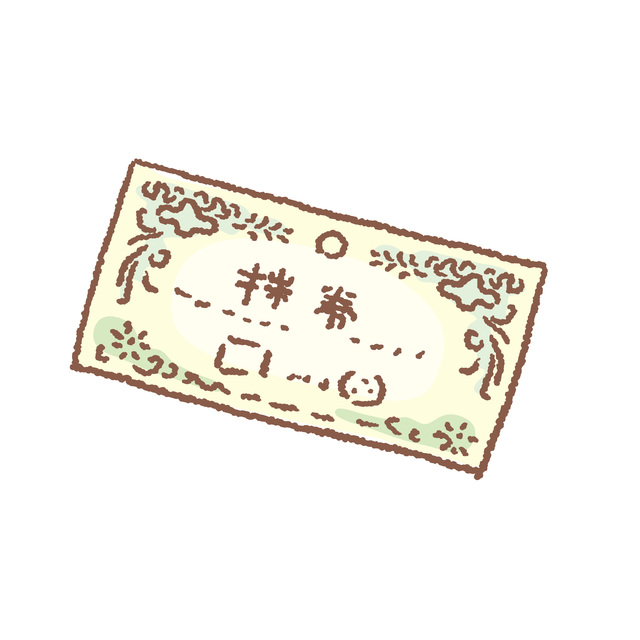遺産分割の際に、葬儀費用の金額や誰が負担するのかについて争いとなることがあります。
葬儀費用とは
葬儀費用とは、葬式(追悼儀式、埋葬など)に要する費用(民法306条3号、309条)と考えられています。
葬式は、被相続人の生前の社会的地位や宗教、葬式の主宰者や相続人の宗教、被相続人やその家族の生活状況、その地方における慣習などにより様々な形態があります。
葬式により発生する費用も多様なものがあります。
仏式の葬式は、通常、通夜⇒告別式⇒火葬⇒初七日・四十九日の法要⇒遺骨の埋葬、という流れで行われます。
その過程で、葬儀会社、僧侶・寺院、火葬場などに対して支払う費用が発生します。
葬儀費用については、以下の点が問題となります。
- 何が葬儀費用に含まれるのか
- 誰が葬儀費用を負担するのか
- 香典との関係
葬儀費用は相続開始後に生じた債務であるため、葬儀費用に関する争いについては、原則として遺産分割の対象ではなく、遺産分割の中で解決できる問題ではありません。
したがって、葬儀費用に関する争いが遺産分割の中で合意できない場合、遺産分割とは別に、民事訴訟手続において解決する必要があります。
遺産分割の対象についてはこちらのページで説明します。
何が葬儀費用に含まれるのか
棺柩その他の祭具・葬儀場の設営・読経・火葬・墓標の費用、通夜・告別式の参列者の飲食代、納骨代などは葬儀費用に含まれます。
これに対し、墓地の代価、葬儀後の見舞客の接待費用などは葬儀費用に含まれません。
初七日・四十九日の法要にかかる費用は、葬儀費用に含まれないと考えられます(東京地裁昭和61年1月28日)。
<東京地裁昭和61年1月28日>
葬式費用とは、死者をとむらうのに直接必要な儀式費用をいうものと解するのが相当であるから、これには、棺柩その他葬具・葬式場設営・読経・火葬の費用、人夫の給料、墓地の代価、墓標の費用等が含まれるのみであつて、法要等の法事、石碑建立等の費用は、これに含まれないと解する。
誰が葬儀費用を負担するのか
被相続人の指示があればそれに従い、また、相続人間で合意ができればそれに従うことになります。
相続人間で合意ができない場合、原則として喪主(喪主が形式的なものである場合、実質的な葬式の主宰者)が負担すると考えられます(前掲東京地裁昭和61年1月28日、東京地裁平成6年1月17日、名古屋高裁平成24年3月29日)。
<前掲東京地裁昭和61年1月28日>
原告は、右葬式費用…は、相続財産に関する費用であり、相続財産が分割承継された場合には、相続人が法定相続分に従い、これを負担すべきであるから、相続人である被告らが法定相続分に従い、右葬式費用を負担すべきであると主張する。
しかしながら、相続財産に関する費用(民法885条)は、相続財産を管理するのに必要な費用、換価、弁済その他清算に要する費用など相続財産についてすべき一切の管理・処分などに必要な費用をいうものと解されるのであつて、死者をとむらうためにする葬式をもつて、相続財産についてすべき管理、処分行為に当たるとみることはできないから、これに要する費用が相続財産に関する費用であると解することはできない。
したがつて、これを前提とする原告の主張は失当である。
また、民法306条3号、309条1項は、債務者の身分に応じてした葬式の費用については、その総財産の上に先取特権が存在する旨規定しているが、これは、貧者にも、死者の身分相応の葬式を営ましめようとの社会政策的な配慮から、身分相応の葬式費用については、その限度で、相続財産(遺産)が担保になる旨規定しているにすぎないど解すべきであつて、これをもつて、葬式費用が相続財産に関する費用であるど解することも、まして、葬式費用の負担者が相続人であると解することもできない。
しかも、仮に、この規定を右のように解するとすれば、身分相応の程度を超えた葬式費用については、規定していないこととなるから、この部分の費用を結局誰れが負担するかについては、また別個に根拠を求めざるを得ないし、たまたま、相続財産が充分に存在する場合は格別、相続財産が皆無か、あるいは、存在しても、身分に相応した葬式費用を負担するに足りないときは、右のように解するどきは、かえつて、債権者に不測の損害を蒙むらせることとなり相当でない。
また、葬式費用を身分に相応した部分とそうでない部分とに区別して、その負担者を別異に取扱うこととなるのも当を得ない。
相続税13条1項2号は、相続財産の価額から被相続人に係る葬式費用を控除した価額につき、相続税が課税される旨規定している。
しかし、右は、葬式費用のうち、相続人の負担に属する葬式費用につき、控除する旨規定していることが明らかであつて、葬式費用を負担しない場合でも、相続財産の価額から葬式費用が当然に控除される旨規定しているものではない。
したがつて、この規定をもつて、葬式費用が相続財産に関する費用であり、相続人が負担するものであると解する根拠とすることはできない。
葬式は、死者をとむらうために行われるのであるが、これを実施、挙行するのは、あくまでも、死者ではなく、遺族等の、死者に所縁ある者である。
したがつて、死者が生前に自已の葬式に関する債務を負担していた等特別な場合は除き、葬式費用をもつて、相続債務とみることは相当ではない。
そして、必ずしも、相続人が葬式を実施するとは限らないし、他の者がその意思により、相続人を排除して行うこともある。
また、相続人に葬式を実施する法的義務があるということもできない。
したがつて、葬式を行う者が常に相続人であるとして、他の者が相続人を排除して行つた葬式についても、相続人であるという理由のみで、葬式費用は、当然に、相続人が負担すべきであると解することはできない。
こうしてみると、葬式費用は、特段の事情がない限り、葬式を実施した者が負担するのが相当であるというべきである。
そして、葬式を実施した者とは、葬式を主宰した者、すなわち、一般的には、喪主を指すというべきであるが、単に、遺族等の意向を受けて、喪主の席に座つただけの形式的なそれではなく、自己の責任と計算において、葬式を準備し、手配等して挙行した実質的な葬式主宰者を指すというのが自然であり、一般の社会観念にも合致するというべきてある。
したがつて、喪主が右のように形式的なものにすぎない場合は、実質的な葬式主宰者が自己の債務として、葬式費用を負担するというべきである。
すなわち、葬式の主宰者として、葬式を実施する場合、葬儀社等に対し、葬式に関する諸手続を依頼し、これに要する費用を交渉・決定し、かつ、これを負担する意思を表示するのは、右主宰者だからである。
そうすると、特別の事情がない限り、主宰者が自らその債務を葬儀社等に対し、負担したものというべきであつて、葬儀社等との間に、何らの債務負担行為をしていない者が特段の事情もなく、これを負担すると解することは、相当てはない。
したがつて、葬式主宰者と他の者との間に、特別の合意があるとか、葬式主宰者が義務なくして他の者のために葬式を行つた等の特段の事情がある場合は格別、そうてない限り、葬儀社等に対して、債務を負担した者が葬式費用を自らの債務として負担すべきこととなる。
香典との関係
香典は、死者の供養のためや遺族の悲しみを慰めるために贈られるものでもありますが、葬式費用に充てることを目的として、葬式の主宰者である喪主に対する贈与と考えられます(前掲東京地裁昭和61年1月28日)。
したがって、葬式の主宰者(喪主)は、香典から香典返しの費用を控除した残りを、葬儀費用に充てることができます。
<前掲東京地裁昭和61年1月28日>
香典とは、葬式費用に充てることを目的として、葬式の主宰者である喪主に対し贈与されるものと解するのが相当であり、したがつて、香典返しも右主宰者において責任をもつて行うものというべき…。
葬儀費用と香典の関係については、以下のように考えられます。
- 香典の額が葬儀費用・香典返しの費用の合計額を超える場合、残額は葬式の主宰者(喪主)が取得します。
- 香典の額が香典返しの費用の合計額に満たない場合、不足額は葬式の主宰者(喪主)の負担となります。