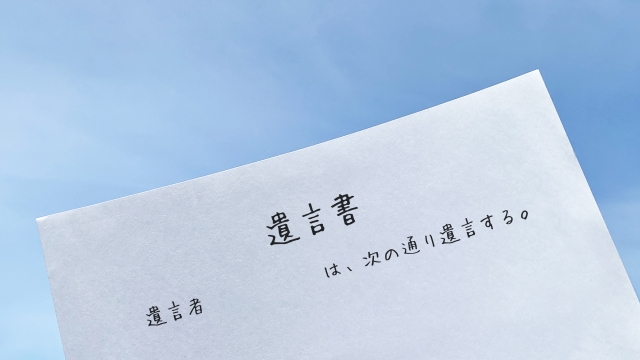遺言で、相続人に財産を取得させる場合、次のような表現がよく利用されます。
- 甲不動産を相続人Bに相続させる
- 全財産を相続人Bに相続させる
- 財産の2/3を相続人Bに、財産の1/3を相続人Bに相続させる
このような遺言は、「相続させる遺言」、「相続させる旨の遺言」と呼ばれています。
「相続させる」ではなく「承継させる」でも意味は同じです。
相続させる遺言は、遺言者が、どのような効力を望んでいたのか必ずしも明らかでなく、効力の判断が難しいこともあります。
以下、場合を分けて説明します。
条文については、特に断りのない限り、民法のものです。
特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言
例えば、「甲不動産を相続人Bに相続させる」という遺言です。
遺産分割方法の指定
被相続人Aが、甲不動産をBに相続させるとの遺言を残して死亡した場合、Aの遺言は、原則として遺産分割方法の指定となります(最高裁平成3年4月19日)。
もっとも、例外的に遺贈となる場合もありますが、遺贈となるのは、遺言書の記載から、①その趣旨が遺贈であることが明らかな場合、②遺贈と解釈すべき特段の事情がある場合、に限られます。
遺産分割方法の指定には、以下の2つの意味があります。
- 権利を移転する効力をもたないもの(本来の意味の遺産分割方法の指定)
- 権利を移転する効力を持つもの(特定財産承継遺言)
以下、それぞれ説明します。
権利を移転する効力をもたないもの
遺産分割方法の指定は、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割という遺産分割方法のうち、どのような方法により遺産分割を行うのかを遺言者が指定する(908条)、というのが本来の意味です。
例えば、以下のような遺言です。
「すべての財産の全部を換価し、一切の債務を弁済した残金を、相続人Bに6/8、相続人Cに1/8、相続人Dに1/8を配分するよう分割の方法を指定する。」
このような遺言は、遺産分割において財産を具体的にどのように配分するのかについての方法を指定するものです。
そのため、遺言自体に権利を移転する効力まではなく、遺産分割によって権利を取得することになります。
もっとも、相続人は、遺言者が指定した遺産分割方法に事実上拘束され、協議・調停・審判での基準ともなります。
権利を取得する効力をもつもの
遺産分割方法の指定には、遺産分割によらずに権利を移転する効力をもつものもあります。
例えば、前に説明した「甲不動産をBに相続させる」との遺言は、Aが死亡することにより、遺産分割をしなくても甲不動産の所有権をBが取得する効力をもちます。
また、特定の財産を当然に特定の相続人が取得する結果、相続分が変わることもあり、その場合には相続分の指定の意味も含まれています。
このように、遺産の分割の方法の指定として、特定の財産を、特定の相続人に承継させる遺言を特定財産承継遺言といいます (1014条2項)。
これに対し、すべての財産又は一定割合の財産を、特定の相続人に承継させる遺言は、特定承継遺言ではなく、相続分の指定となります。
相続分の指定については、後に説明します。
法定相続分との関係
特定の財産の価額が法定相続分を超える場合
例えば、被相続人Aが、「甲不動産(遺産の3/4の価値)をBに相続させる」との遺言を残して死亡し、相続人が妻B、子C・Dの場合、甲不動産の価額は、Bの法定相続分1/2を超えています。
Aが死亡すると、甲不動産はBが取得するため、遺産分割の対象ではなくなります。
そして、Bの法定相続分を超える相続分の指定も含まれています。
したがって、Bは残りの遺産についての相続分はなく、C・Dが残りの遺産を取得することになります。
特定の財産の価額が法定相続分を下回る場合
例えば、被相続人Aが、「甲不動産(遺産の1/5)をBに相続させる」との遺言を残して死亡し、相続人が妻B、子C・Dの場合、甲不動産の価額は、Bの法定相続分1/2を下回ります。
Aが死亡すると、甲不動産はBが取得するため、遺産分割の対象ではなくなります。
そして、Bの法定相続分を下回る相続分の指定が含まれていますが、その意味については次のどちらの意味であるかが問題となります。
▶Bの法定相続分を下回る相続分の指定
Bが取得する1/5を除いた残りの4/5をC・Dが法定相続分に応じて取得することになり、Bは1/5、C・Dは4/5×1/2=2/5を取得することになります。
▶Bには1/5の先取りを認める相続分の指定
Bが先取りする1/5を除いた残りの4/5をB・C・Dが法定相続分に応じて取得することになり、Bは1/5+4/5×1/2=3/5、C・Dは4/5×1/4=1/5を取得することになります。
権利の取得と対抗要件
不動産
従来、相続させる遺言により不動産を取得した場合、法定相続分を超えるときでも、登記をしなくても第三者に対抗できました(最高裁平成5年7月19日、最高裁平成14年6月10日)。
しかし、民法の改正により、相続による権利の承継(遺産分割のほかに、財産承継遺言や相続分の指定も含まれます。)は、法定相続分を超える部分については、対抗要件(登記など)を備えなければ、第三者に対抗することができないことになりました(899条の2第1項)。
したがって、相続させる遺言により不動産を取得した場合、法定相続分を超えるときは、登記をしなければ第三者に対抗できません。
債権
債権を承継した場合の対抗要件は、債権の譲渡人から債務者に対する通知か債務者の承諾です(467条)。
したがって、相続させる遺言により債権を取得した場合、法定相続分を超えるときは、譲渡人から債務者に対する通知か債務者の承諾がなければ第三者に対抗できません(899条の2第1項)。
もっとも、法定相続分を超えて債権を承継した相続人がその債権に関する遺言の内容(遺産分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をした場合、相続人の全員から債務者に対する通知をしなくても、対抗要件を備えたことになります(899条の2第2項)。
遺言執行者の権利
特定財産承継遺言があった場合、遺言執行者は、共同相続人が対抗要件(899条の2第1項)を備えるために必要な行為をすることができます(1014条2項)。
全財産を特定の相続人に相続させる遺言
例えば、「すべての財産をBに相続させる」との遺言です。
「すべての財産をBに相続させる」との遺言があった場合、特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言と同様に、(権利を取得する効力をもつ)遺産分割方法の指定とともに、相続分の指定が含まれており、すべての財産が遺産分割の対象ではなくなります(最高裁平成21年3月24日)。
したがって、遺産分割は必要ない(できない)ことになります。
この場合、相続人の遺留分が侵害されているときは、相続人は遺留分侵害額を請求することになります。
従来、遺留分減殺の対象は遺贈と贈与に限定され(改正前1031条)、相続分の指定は遺留分に関する規定に違反できないとされていました(改正前902条1項但書)。
しかし、民法の改正により、遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継した相続人や相続分の指定を受けた相続人を含みます。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することが明確になりました(1046条1項)。
したがって、相続分の指定を受けた相続人も遺留分侵害額の請求の相手方となることが明確になりました。
一定の割合の財産を特定の相続人に相続させる遺言
例えば、「相続人Bに財産の2/3を、相続人Cに財産の1/3を相続させる」との遺言です。
相続分の指定
一定割合の財産を、特定の相続人に承継させる遺言は、相続分の指定となります。
相続分の指定とは、法定相続分とは異なる相続分の割合を定めることをいいます(902条1項)。
被相続人が特定の相続人の相続分を定めた場合、他の相続人の相続分は法定相続分となります(902条2項)。
相続分の指定をしただけでは、原則として相続人が直ちに財産を取得する効力まではなく、指定された相続分の範囲で、誰がどの財産を取得するのかについて遺産分割をする必要があります。
もっとも、相続分の指定により、相続人が直ちに財産を取得する効力があり、遺産分割をする必要がない場合もあります。
遺言者が、相続人に直ちに財産を取得させることまで意図していたかどうか、遺言書の内容から判断が難しい場合もあります。
例えば、「相続人Bに財産の2/3を、相続人Cに財産の1/3を相続させる」との遺言があった場合、相続人による遺産分割を予定していたのか、遺産分割を予定せずに相続人に直ちに共有持分を取得させる意図だったのか、判断が難しい場合があります。
遺産分割を予定していると考える場合
遺言者の意思は、遺産全体から指定した割合の価値に相当する額を取得させる意思であり、そのような価値に相当する額を取得させるため、具体的な配分は遺産分割により決定することになります。
遺産分割を予定していないと考える場合
遺言者の意思は、遺産全体を指定した割合で共有取得させる意思であり、遺産分割をしなくても、相続人が共有持分を取得することになります。
この場合、共有状態を解消するためには、遺産分割ではなく共有物分割(256条)をすることになります。
公正証書遺言は、「具体的な財産の配分については相続人の協議によって定める。」といった記載があるなどの特段の事情がない限り、「相続させる遺言」は遺産分割をすることなく、記載された割合での共有(準共有)持分を取得する趣旨で作成されているようです。
したがって、「被相続人Aが相続人Bに財産の2/3を、相続人Cに財産の1/3を相続させる」との遺言を残して死亡し、Aの遺産が甲不動産と乙銀行の預金300万円だった場合、Bは甲不動産の2/3の共有持分と乙銀行の預金200万円、Cは甲不動産の1/3の共有持分と乙銀行の預金100万円を取得することになります。
相続分の指定と対抗要件
前に説明したように、民法の改正により、相続による権利の承継(遺産分割のほかに、財産承継遺言や相続分の指定も含まれます。)は、法定相続分を超える部分については、対抗要件(登記など)を備えなければ、第三者に対抗することができないことになりました(899条の2第1項)。
相続分の指定と債務
被相続人の債務の債権者は、相続分の指定がされた場合であっても、各相続人に対し、法定相続分に応じて権利を行使することができます(902条の2本文)。
例えば、被相続人Aが、「すべての財産をBに相続させる」との遺言を残して死亡し、相続人が妻B、子C・Dの場合、Aに対して1000万円の債権をもつDは、Bに対して500万円、C・Dに対してそれぞれ250万円を請求できます。
もっとも、その債権者が共同相続人のひとりに対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、法定相続分に応じた権利を行使することはできません(902条の2但書)。
例えば、被相続人Aが、「すべての財産をBに相続させる」との遺言を残して死亡し、相続人が妻B、子C・Dの場合、Aに対して1000万円の債権をもつDは、Bが1000万円の債務を承継したことを承認し、Bに対して1000万円を請求できます。
そして、Dは、Bが1000万円の債務を承継したことを承認したときは、C・Dに対してそれぞれ250万円を請求できません。
相続させる遺言と代襲相続
相続させる遺言をした遺言者は、原則として、遺言時に特定の相続人に遺産を取得させる意思があったにすぎず、遺言により遺産を相続させる相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合、その相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる意思があったといえる特段の事情のない限り、相続させる遺言の効力は生じません(最高裁平成23年2月22日)。
例えば、被相続人Aが、「甲不動産をBに相続させる」との遺言を残し、Aが死亡する前にBが死亡した場合、原則としてBの子bが甲不動産を代襲相続することはできません。
そこで、BがAの死亡以前に死亡した場合に、bに甲不動産を相続させたいのであれば、BがAの死亡以前に死亡した場合に備え、bに相続させる補充の遺言を用意する必要があります。