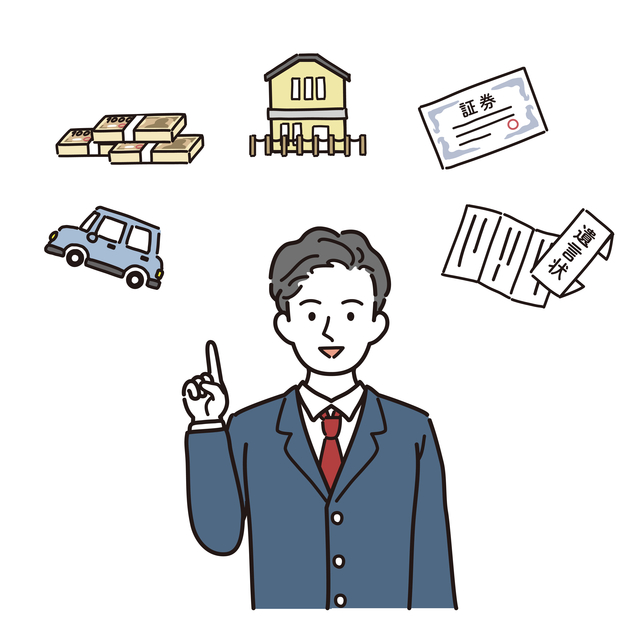遺言には、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条、971条)などがあります。
このうち、遺言書が本文・日付・氏名を自書・押印して作成する自筆証書遺言について解説します。
条文については、特に断りのない限り、民法のものです。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言が有効となる要件は次のとおりです(968条1項)。
この方式に従わないと自筆証書遺言は無効となります。
- 全文、日付、氏名を自書する
- 押印する
以下、それぞれについて説明します。
全文、日付、氏名を自書する
全文
全文とは、すべての本文という意味です。
もっとも、後に説明しますが、民法の改正により、相続財産の特定に必要な事項(財産目録)は、自書する必要がなくなりました(968条2項)。
日付
複数の遺言書がある場合にどれが新しいものかなどを判断するために、暦上の特定の日を表示することが必要です。
裁判例では、「昭和41年7月吉日」と書かれた自筆証書遺言が無効となりました(最高裁昭和54年5月31日)。
氏名
誰の遺言であるかを判断するために、氏と名を併記するのが原則ですが、氏又は名だけであっても遺言者本人を識別できれば差し支えありません。
自書
自書とは、自分で手書きするという意味です。
したがって、全文・日付・氏名をすべて手書きする必要があります。
自書といえるには、自書能力(遺言者が文字を知り、かつ、文字を筆記する能力)が必要です(最高裁昭和62年10月8日)。
裁判例では、運筆(筆の動かし方)について他人の添え手による補助を受けた場合、①遺言者が遺言書の作成時に自書能力を有し、②補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、③添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できるときは、自書といえるとされました(最高裁昭和62年10月8日)。
民法の改正により、相続財産の特定に必要な事項(財産目録)は、自書する必要がなくなり(968条2項)、以下のような方法も有効となります。
- パソコンで作成した一覧表を印刷する
- 登記簿のコピー
- 預貯金通帳のコピー
もっとも、財産目録を自書しない場合、財産目録の各葉(財産目録のすべての用紙)に、署名押印することが必要です(968条2項)。
そして、自書によらない記載が両面にあるときは、両面に署名押印することが必要です。
押印する
印鑑の種類
実印である必要はありません。
認印・三文判・拇指その他の指頭に墨、朱肉などをつけて押捺する指印でも差し支えありません(最高裁平成元年2月16日)。
もっとも、花押(署名の代わりに使用される記号・符号)を書くことは、押印とは認められません(最高裁平成28年6月3日)。
押印の場所
通常は署名の近くに押印します。
もっとも、裁判例では、遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印せず、遺言書であることを意識して、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印した場合でも、自筆証書遺言は有効とされました(最高裁平成6年6月24日)。
契印・封印
契印(2枚以上の契約書が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押印したもの)・封印(封じ目に押印したもの)は必要ありません。
自筆証書遺言の訂正・撤回の方法
加除・訂正
自筆証書遺言を加除・訂正する場合、①その場所を指示、②変更したことを附記、③特に署名、④変更場所に押印する必要があります(968条3項)。
撤回
自筆証書遺言も公正証書遺言も、法律で定められた方式でいつでも撤回できます(1022条)。
公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回・変更することもできます。
次のような場合、遺言を撤回したとみなされます。
- 前後の遺言の内容が抵触する場合(1023条1項)
- 遺言の内容と生前処分とが抵触する場合(1023条2項)
- 遺言書を故意に破棄した場合(1024条前段)
- 遺贈の目的物を故意に破棄した場合(1024条後段)
赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引くことは、「故意に遺言書を破棄」(1024条後段)に該当します(最高裁平成27年11月20日)。
また、遺言が撤回された場合、遺言を撤回する行為が撤回されても、元の遺言の効力は原則として復活しません(1025条本文)。
もっとも、遺言を撤回した遺言者が、更に撤回した遺言を撤回した場合、遺言書の記載から、遺言者の意思が元の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、遺言者の元の遺言の効力が復活します(最高裁平成9年11月13日)。
例えば、被相続人Aが、①甲遺言を作成、②その後に乙遺言を作成し、乙遺言の中に「この遺言書以前に作成した遺言書はその全部を取り消す」と記載し、③その後に丙遺言を作成し、丙遺言の中に「乙遺言はすべて無効とし甲遺言を有効とする」と記載した場合、甲遺言が有効な遺言となります。
自筆証書遺言を作成する場合、過去にも遺言書を作成していた場合に備えて、「遺言者は、本日以前における遺言書の遺言をすべて撤回し、改めて以下のとおり遺言する」などと記載して遺言を撤回し、改めて遺言をしておくことが望ましいです。
自筆証書遺言の保管の方法
遺言書を保管する方法には、遺言者が自ら保管する場合と相続人や第三者に預ける場合があります。
遺言者が死亡した時、遺言書の存在を相続人に知ってもらうことが必要です。
民法の改正により、令和2年7月10日以降、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうこともできます。
以下、説明します。
保管の方法については、法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)で定められています。
遺言書の保管の申請
保管の申請の対象となるのは、封のされていない法務省令で定める様式に従って作成された自筆証書遺言のみです(遺言書保管法1条、4条2項)。
申請の場所は、遺言者の住所地か本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局です(遺言書保管法4条3項)。
遺言者が法務局に自ら出頭し、申請人が本人であるかどうかの確認を受ける必要があります(遺言書保管法4条6項、遺言書保管法5条)。
遺言書の保管の申請には手数料3900円がかかります(遺言書保管法12条1項1号)。
遺言書の保管・情報の管理
法務局の施設内において原本を保管し、その画像情報などの遺言書の情報を管理します(遺言書保管法6条1項・7条1項・2項)。
遺言者による遺言書の閲覧
遺言者は、保管されている遺言書の閲覧を請求することができますが(遺言書保管法6条)が、遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧などをすることはできません。
遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書の交付の請求をするには、手数料1400円(原本の閲覧は1700円)がかかります(遺言書保管法12条1項2号・3号)。
保管の申請の撤回
遺言者は、保管されている遺言書の保管の申請を撤回することができます(遺言書保管法8条1項)。
保管の申請が撤回されると、遺言者に遺言書が返還され、遺言書の情報も消去されます(遺言書保管法8条4項)。
遺言書の保管の有無の照会・相続人等による証明書の請求など
誰でも、自己が相続人・受遺者などになっている遺言書が法務局に保管されているかどうかを証明する書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求できます(遺言書保管法10条1項)。
遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには、手数料800円がかかります(遺言書保管法12条1項3号)。
相続人・受遺者などは、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付・遺言書原本の閲覧を請求できます(遺言書保管法9条1項)。
遺言書情報証明書が交付されたり、遺言書の閲覧がされた場合、法務局から遺言者の相続人・受遺者・遺言執行者に遺言書を保管している旨が通知されます(遺言書保管法9条5項)。
自筆証書遺言を見つけたときの対処方法
検認
自筆証書遺言の保管者や遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に検認の請求をする必要があります(1004条1項)。
もっとも、法務局に保管されている遺言書については、 遺言書の検認は必要ありません(遺言書保管法11条)。
また、公正証書遺言も、検認は必要ありません(1004条2項)。
検認の請求があると、家庭裁判所は、検認をする日を指定して、相続人に通知します。
相続人は、検認の手続きに立合うことができます。
検認は、家庭裁判所で遺言書の内容を確認し、その後の遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
そのため、検認をしたからといって、遺言が有効だということにはなりません。
検認をせずに遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられます(1005条)。
開封
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いの下で開封する必要があります(1004条3項)。
もっとも、検認前に開封しただけでは遺言は無効にはなりません。
開封後でも家庭裁判所に検認の申し立てはできます。
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合、相続する権利がなくなります(891条5号)。
自筆証書遺言の効力に疑問がある場合
例えば、遺言書が自書されたものであるか疑問があるなど、自筆証書遺言の効力に疑問がある場合、遺言の無効確認を求める訴訟によって、自筆証書遺言が有効となるかどうかについて決める必要があります。
そして、遺言の無効確認を求める訴訟においては、自筆証書遺言が民法968条の定める方式に則って作成されたものであることを、遺言が有効であると主張する側が主張・立証する責任があります(最高裁昭和62年10月8日)。