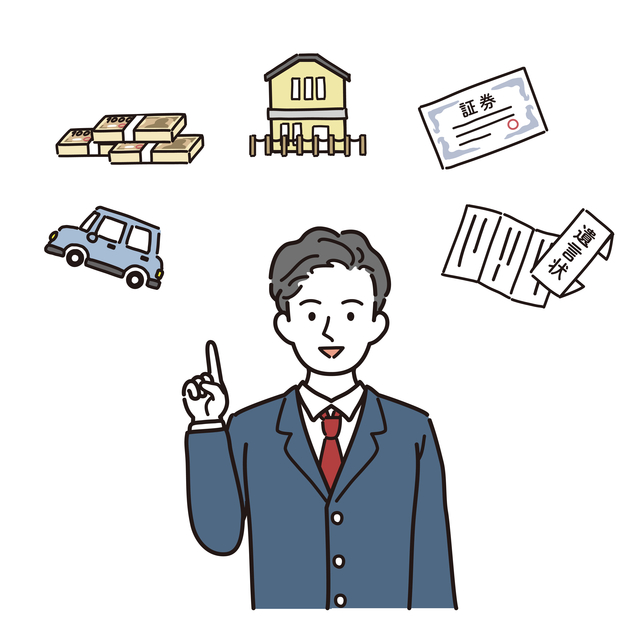遺言の文言からは遺言者の意思が明確でない場合、どのように遺言の内容を解釈すべきかが問題となります。
解釈の指針
遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定の条項を解釈するにあたっても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきであるとされています(最高裁昭和58年3月18日)。
もっとも、遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈できる場合,遺言書に表われていない事情を遺言の意思解釈の根拠とすることは許されないとされています(最高裁平成13年3月13日)。
<最高裁昭和58年3月18日>
上告人ら[弟妹]が本訴において主張するところは、…主位的請求原因として、Iは、本件遺言書において、妻である被上告人の死亡を停止条件として、弟妹である上告人…及び…に対し…本件不動産…の持分各10分の1、…に対し同持分20分の3をそれぞれ遺贈する旨の遺言をした、I は…死亡し、右のとおり遺贈の効力が生じた、…被上告人[妻]は、Iから本件不動産の単純遺贈を受けたものとして、本件不動産につき…遺贈を原因とする自己単独名義の所有権移転登記を経由した、…よって、上告人ら[弟妹]は、被上告人[妻]との間において、上告人ら[弟妹]がIから前記のとおりの遺贈を受けたことの確認を求めるとともに、被上告人[妻]に対し、右登記の抹消登記手続を求める、というのであり、…予備的請求原因として、…Iの遺言のうち本件不動産の遺贈に関する部分は、内容が不明確であって、遺言者Iの真意を把握することができないから無効である、…よって、上告人ら[弟妹]は、被上告人[妻]との間において、右遺言部分が無効であることの確認を求める、というのである。
…遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。
…原審は、本件遺言書の中から第1次遺贈及び第2次遺贈の各条項のみを抽出して、「後継ぎ遺贈」という類型にあてはめ、本件遺贈の趣旨を前記のとおり解釈するにすぎない。
…右遺言書の記載によれば、Iの真意とするところは、第1次遺贈の条項は被上告人[妻]に対する単純遺贈であって、第2次遺贈の条項はIの単なる希望を述べたにすぎないと解する余地もないではないが、本件遺言書による被上告人[妻]に対する遺贈につき遺贈の目的の一部である本件不動産の所有権を上告人ら[弟妹]に対して移転すべき債務を被上告人[妻]に負担させた負担付遺贈であると解するか、また、上告人ら[弟妹]に対しては、被上告人[妻]死亡時に本件不動産の所有権が被上告人[妻]に存するときには、その時点において本件不動産の所有権が上告人ら[弟妹]に移転するとの趣旨の遺贈であると解するか、更には、被上告人[妻]は遺贈された本件不動産の処分を禁止され実質上は本件不動産に対する使用収益権を付与されたにすぎず、上告人ら[弟妹]に対する被上告人[妻]の死亡を不確定期限とする遺贈であると解するか、の各余地も十分にありうるのである。
原審としては、本件遺言書の全記載、本件遺言書作成当時の事情などをも考慮して、本件遺贈の趣旨を明らかにすべきであったといわなければならない。
<最高裁平成13年3月13日>
遺言の意思解釈に当たっては、遺言書の記載に照らし、遺言者の真意を合理的に探究すべきところ、本件遺言書には遺贈の目的について単に「不動産」と記載されているだけであって、本件土地を遺贈の目的から明示的に排除した記載とはなっていない。
一方、本件遺言書に記載された「●●7丁目60番4号」は、Tの住所であって、同人が永年居住していた自宅の所在場所を表示する住居表示である。
そして、本件土地の登記簿上の所在は「●●7丁目」、地番は「158番6」であり、本件建物の登記簿上の所在は「●●7丁目158番地6」、家屋番号は「158番6の1」であって、いずれも本件遺言書の記載とは一致しない。
…そうすると、本件遺言書の記載は、Tの住所地にある本件土地及び本件建物を一体として、その各共有持分を上告人に遺贈する旨の意思を表示していたものと解するのが相当であり、これを本件建物の共有持分のみの遺贈と限定して解するのは当を得ない。
原審は、…本件遺言書作成当時の事情を判示し、これを遺言の意思解釈の根拠としているが、以上に説示したように遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈し得る本件においては、遺言書に表われていない…事情をもって、遺言の意思解釈の根拠とすることは許されないといわなければならない。
問題となった事例
財産をまかせる
「財産をまかせる」という遺言について、遺贈にあたらないとした裁判例(東京高裁昭和61年6月18日)と遺贈にあたるとした裁判例(大阪高裁平成25年9月5日)とがあります。
<東京高裁昭和61年6月18>
…Iは、昭和35年ころ茶道を通じて訴外人と知り合い、それ以来交際を続けていたが、昭和54年9月30日妻…が死亡してからは訴外人を思う気持ちが募り昭和55年ころには結婚を申し込むなどその交際は深まっていったところ、昭和56年9月10日…病院に入院するに当たり、その前日である9日、H家の財産は全部訴外人にまかせる旨を記載した本件遺言書…を作成し、これを訴外人に交付した…。
…次に、前記遺言が本件土地を訴外人に遺贈する趣旨を含むものであるか否かにつき検討するに、…本件遺言書にはH家の財産は全部訴外人に「まかせます」との記載があるけれども、「まかせる」という言葉は、本来「事の処置などを他のものにゆだねて、自由にさせる。相手の思うままにさせる。」ことを意味するにすぎず、与える(自分の所有物を他人に渡して、その人の物とする。)という意味を全く含んでいないところ、本件全証拠によってもIの真意が訴外人に本件土地を含むその所有の全財産を遺贈するにあつたと認めるには足りない。
すなわち…、…Iが訴外人に結婚を申し込んだものの、訴外人において年老いた母親の面倒をみていたことなどから実現するに至らず、同棲はもちろん婚姻届出もしておらず…、せいぜい訴外人が時折Iのもとを訪れて身辺の世話をするという関係に止どまっていたにすぎず、Iがその所有にかかる全財産を遺贈してでも感謝の気持ちを表すのが当然であるといえるような関係にあったものではないこと、Iは昭和43年12月1日妻…に対し全財産を与える旨の遺言証書と題する書面によって自筆証書遺言をしたことがあったが、これはその以前にも同様の遺言書を作成していたものを念のため再度作成したものであること(したがって、Iは遺言書及び遺贈につき十分な知識を有していたと推認できる。)、本件遺言書は昭和43年の遺言書とは異なり、ごく粗末なメモ書きといつた体裁のものにすぎず、入院前の慌ただしい時に作成したためそうなったものとしても、その後より正式な問題のない体裁内容のものに書き直す時間的余裕が十二分にあったにもかかわらずそれがなされていないこと、他方、控訴人はIの一人娘であって他にIの相続人はおらず、控訴人がIの反対を押し切って結婚したことがあり、また昭和45年ころからIと別居していて親子関係が必ずしもしっくりいつていなかった面があつたものの、全くの断絶状態にあったわけではなく、Iの孫である控訴人の長男Nとは何らのわだかまりもない交流があり、控訴人も時々はI宅を訪れ、なにくれとなくその身の回りの世話をしていたことなどからしても、実の娘に何らの財産も遺さないような遺言をするような状況にはなかった…。
右認定の事実関係によると、Iが本件遺言によって本件土地を含む全財産を訴外人に遺贈する意思を表示したものと認めることは困難である。
…本件遺言書に先立ち「譲る」と記載した遺言書を作成しようとした事実があつたとしても、むしろ、遺贈につき確定的な意思表示をすることを避けたものと考えられ、Iの本件遺言の真意が全財産を訴外人に遺贈するにあったものと認めることはできない。
<大阪高裁平成25年9月5日>
…Aは、平成15年2月から、妻Hと共に、大阪府河内長野市内に所在するZに入居し、本件遺言をした平成17年11月11日当時もZに入居していたが、Zに入居中のA夫婦のもとをしばしば訪れて、その世話をしていたのは専ら…に居住する控訴人である。
他方、参加人夫婦は、A夫婦との関係が円滑さを欠くようになったため、…自宅を出て、A夫婦と別居した後は、A夫婦と疎遠な関係になり、本件遺言がされた当時は、ほとんど交流が途絶えていた。
また、Tも、遠方に居住している関係で、年2、3回程度しかA夫婦のもとを訪れることができなかった。そのような事情があったため、本件遺言をした当時、AがA夫婦の世話やA死亡後のHの世話を頼めるのは控訴人しかおらず、Aは、控訴人を信頼し、頼りにしていた。
このことは、Aが、平成16年9月6日に、郵便貯金の解約等の手続を控訴人に委任したり、本件遺言をした後である平成18年7月12日に控訴人に対し、700万円を贈与したりしていることからも窺い知ることができる。
遺産は公共に寄与する
「…遺産は一切の相続を排除し、…全部を公共に寄与する。」との遺言について、公共のために利用されるという目的を達成することのできる団体等(国・地方公共団体・公益法人・学校法人・社会福祉法人等)にその遺産の全部を包括遺贈する趣旨であり、遺言執行者に対してそのような団体等の中から受遺者として特定のものを選定することをゆだねる趣旨を含むとした裁判例があります(最高裁平成5年1月19日)。
なお、この裁判例は、遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきだが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが遺言者の意思に沿うものであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるとしています。
<最高裁平成5年1月19日>
…亡Aの法定相続人は、いずれも妹である上告人らだけであったが、後記の本件遺言がされた時点では、Aと上告人らとは長らく絶縁状態にあった。
…Aは、昭和58年2月28日、被上告人に遺言の執行を委嘱する旨の自筆による遺言証書(…本件遺言執行者指定の遺言書…)を作成した上、これを被上告人に託するとともに、再度その来宅を求めた。
…Aは、同年3月28日、右の求めに応じて同人宅を訪れた被上告人の面前で、「一、発喪不要。二、遺産は一切の相續を排除し、三、全部を公共に寄與する。」という文言記載のある自筆による遺言証書(…本件遺言書…)を作成して本件遺言をした上、これを被上告人に託し、自分は天涯孤独である旨を述べた。
…被上告人は、Aが昭和60年10月17日に死亡したため、翌61年2月24日頃、東京家庭裁判所に本件遺言執行者指定の遺言書及び本件遺言書の検認を請求して同年4月22日にその検認を受け、翌23日、上告人らに対し、Aの遺言執行者として就職する旨を通知した。
…遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものというべきである。
このような見地から考えると、本件遺言書の文言全体の趣旨及び同遺言書作成時のAの置かれた状況からすると、同人としては、自らの遺産を上告人ら法定相続人に取得させず、これをすべて公益目的のために役立てたいという意思を有していたことが明らかである。
そして、本件遺言書において、あえて遺産を「公共に寄與する」として、遺産の帰属すべき主体を明示することなく、遺産が公共のために利用されるべき旨の文言を用いていることからすると、本件遺言は、右目的を達成することのできる団体等(原判決の挙げる国・地方公共団体をその典型とし、民法34条に基づく公益法人あるいは特別法に基づく学校法人、社会福祉法人等をも含む。)にその遺産の全部を包括遺贈する趣旨であると解するのが相当である。
また、本件遺言に先立ち、本件遺言執行者指定の遺言書を作成してこれを被上告人に託した上、本件遺言のために被上告人に再度の来宅を求めたという前示の経緯をも併せ考慮すると、本件遺言執行者指定の遺言及びこれを前提にした本件遺言は、遺言執行者に指定した被上告人に右団体等の中から受遺者として特定のものを選定することをゆだねる趣旨を含むものと解するのが相当である。
このように解すれば、遺言者であるAの意思に沿うことになり、受遺者の特定にも欠けるところはない。
そして、前示の趣旨の本件遺言は、本件遺言執行者指定の遺言と併せれば、遺言者自らが具体的な受遺者を指定せず、その選定を遺言執行者に委託する内容を含むことになるが、遺言者にとって、このような遺言をする必要性のあることは否定できないところ、本件においては、遺産の利用目的が公益目的に限定されている上、被選定者の範囲も前記の団体等に限定され、そのいずれが受遺者として選定されても遺言者の意思と離れることはなく、したがって、選定者における選定権濫用の危険も認められないのであるから、本件遺言は、その効力を否定するいわれはないものというべきである。