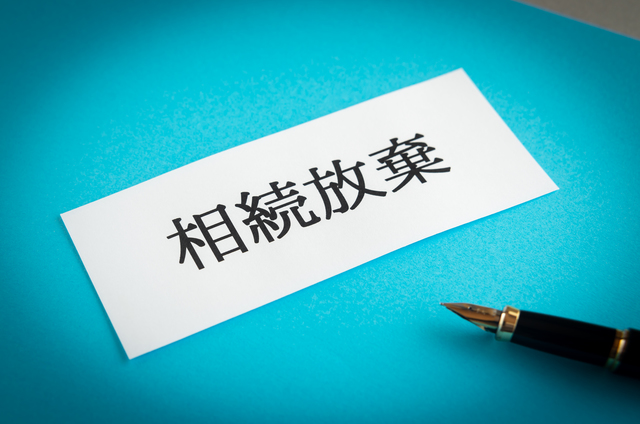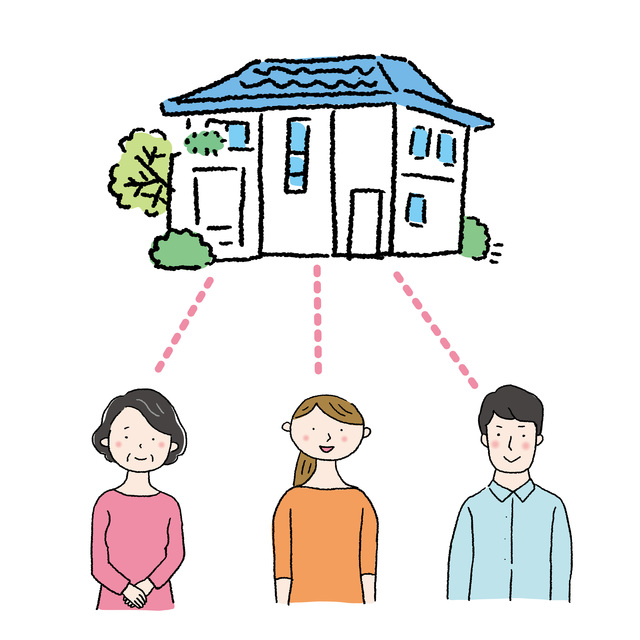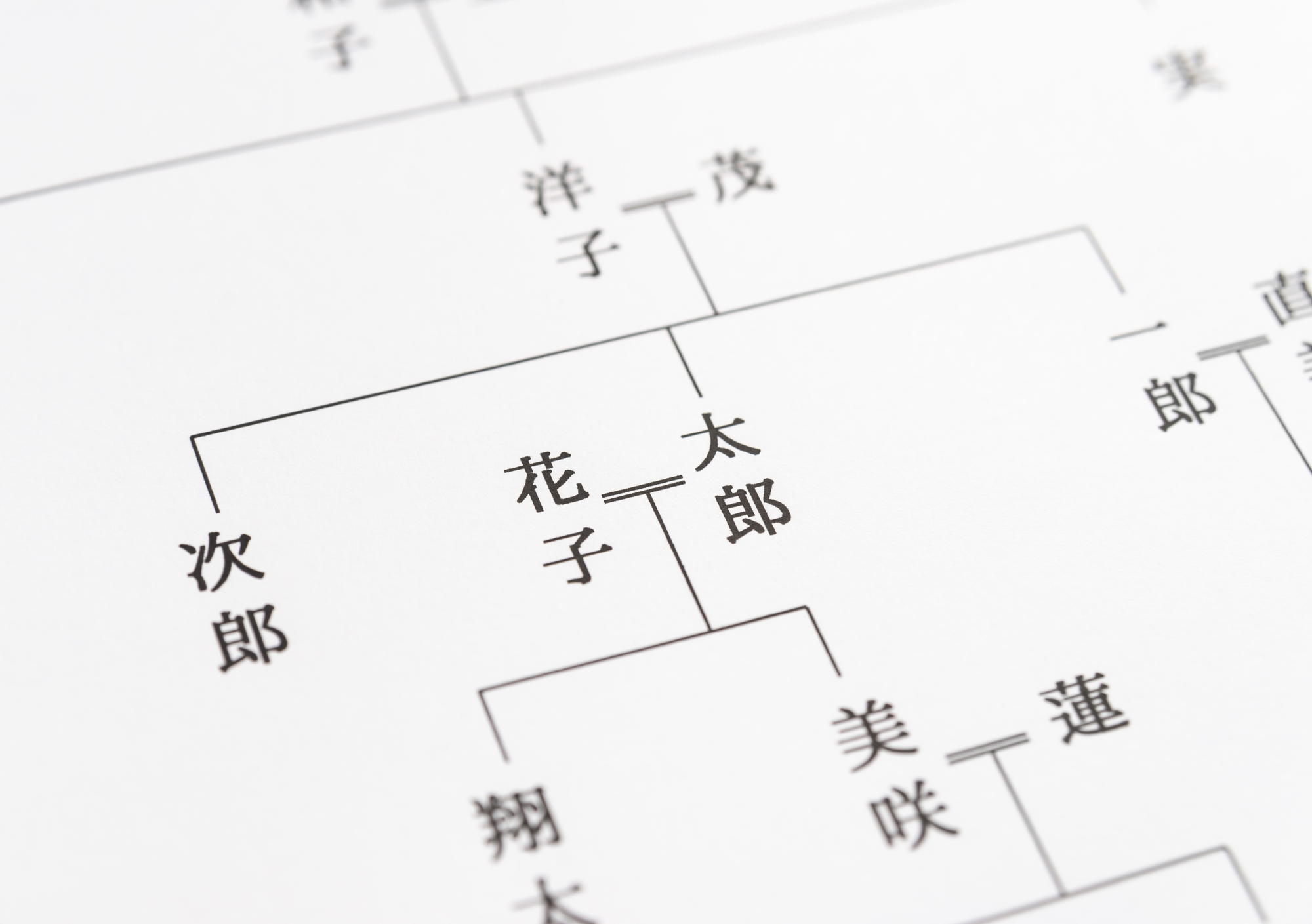寄与分とは
相続人が、身分関係や親族関係から通常期待される以上に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、特別の寄与を評価して算出した割合や金額を考慮して遺産分割を行います(民法904条の2)。
特別の寄与を評価して算出した割合や金額を寄与分といいます。
民法の改正により、相続人でない親族の貢献を考慮するため、特別寄与料という制度もできました。
特別寄与料については、こちらのページで説明します。
寄与分をどのように考慮するのか
被相続人が相続開始時にもっていた財産の価額から寄与分額を控除たものを遺産とみなし、各相続人の相続分を算出した後に、寄与分のある相続人に寄与分額を加算して遺産分割を行います。
寄与分の評価時点は、相続開始時です。
例えば、被相続人Aが5000万円の財産を残して死亡し、相続人が妻B、長男C、長女Dの場合、長男Cに500万円の寄与分があるときは、各相続人の取得額は以下のようになります。
- 遺産とみなされる額=5000万円-500万円=4500万円
- B=4500万円×1/2=2250万円
- C=4500万円×1/2×1/2+500万円=1625万円
- D=4500万円×1/2×1/2=1125万円
寄与分が認められる場合
寄与分が認められるのは、次のすべてに該当する場合です(民法904条の2)。
- 特別の寄与をしたこと
- 被相続人の遺産が維持又は増加したこと
- 特別の寄与と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること
以下、個別に説明します。
特別の寄与をしたこと
被相続人と相続人との身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をしたことが必要です。
夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、親族間の互助義務(民法730条)・扶養義務(民法877条1項)の範囲内の行為は、特別の寄与にはなりません。
特別の寄与となる貢献の程度は、被相続人と相続人の身分関係によって差があります。
例えば、配偶者と子供が同じ程度の貢献をした場合、妻については夫婦の協力扶助義務の範囲内として特別の寄与が認められなくても、親族間の互助義務・扶養義務を負うにすぎない子供については、特別の寄与が認められる場合もあります。
被相続人の財産が維持又は増加したこと
特別の寄与がなければ生じたはずの被相続人の財産の減少や債務の増加が防止されたり、生じなかったはずの被相続人の財産の増加や債務の減少があることが必要です。
特別の寄与と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること
精神的な援助・協力が存在するだけでは、因果関係があるとはいえません。
遺留分との関係
寄与分の額には上限の定めがないことから、遺贈を控除した額の範囲内であれば、遺留分を侵害する寄与分を定めることもできます。
もっとも、裁判所は、寄与分を定めるにあたり遺留分を考慮すべきと考えられます(東京高裁平成3年12月24日)。
<東京高裁平成3年12月24日>
寄与分の制度は、相続人間の衝平を図るために設けられた制度であるから、遺留分によって当然に制限されるものではない。
しかし、民法が、兄弟姉妹以外の相続人について遺留分の制度を設け、これを侵害する遺贈及び生前贈与については遺留分権利者及びその承継人に減殺請求権を認めている(1031条)一方、寄与分について、家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定める旨規定していること(904条の2第2項)を併せ考慮すれば、裁判所が寄与分を定めるにあかっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべきは当然である。
確かに、寄与分については法文の上で上限の定めがないが、だからといって、これを定めるにあたって他の相続人の遺留分を考慮しなくてよいということにはならない。
むしろ、先に述べたような理由から、寄与分を定めるにあたっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである。
寄与分の対象となる具体的な行為
寄与分の対象となる行為の種類には、次のものがあります。
- 家業従事型:被相続人が経営する事業や農業に従事した場合
- 金銭等出資型:被相続人に財産上の利益を給付する場合
- 療養看護型:病気療養中の被相続人の療養看護に従事した場合
- 扶養型:被相続人を扶養した場合
- 財産管理型:被相続人の財産を管理した場合
このうち、問題となることが多い家業従事型と療養看護型について説明します。
家業従事型
家業である農業や商工業など被相続人の事業に労務を提供した場合です。
被相続人の営む会社への労務提供は、あくまでも会社に対する貢献であり、原則として特別の寄与とは認められません。
特別の貢献
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超えていることが必要です。
無償性
完全な無償ではなくても、世間一般並みの労働報酬に比べて著しく少額であれば無償と評価できることがあります。
この点、以下のような裁判例があります。
<大阪高裁平成2年9月19日>
被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが遺産分割にあたって評価されるのは、寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないから、被相続人の事業に関して労務を提供した場合、提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは、寄与分と認めることはできないが、支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは、報いられていない残余の部分については寄与分と認められる余地があると解される。
これに対し、無給かそれに近い状態であっても、 被相続人の資産や収入で生活していれば 無償と評価できないこともあります。
この点、以下のような裁判例があります。
<札幌高裁平成27年7月28日>
平成18年×月までの前記郵便局の業務主体は被相続人であったこと、給与水準は従事する事業の内容、企業の形態、規模、労働者の経験、地位等の諸条件によって異なるから、…大卒46歳時の年収の平均額に充たなかったとしても、被抗告人B夫婦の収入が低額であったとはいえず、むしろ月25万円から35万円という相応の収入を得ていたことが認められること、更に被抗告人B夫婦は被相続人と同居し、家賃や食費は被相続人が支出していたことをも考慮すると、被抗告人Bは、上記郵便局の事業に従事したことにより相応の給与を得ていたというべきであり、被抗告人Bの郵便局事業への従事が、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたとは認められない。
継続性
労務の提供が一定以上の期間に及んでいることが必要です。
期間については明確な定めがあるわけでは なく、一切の事情を考慮して個別に判断されることになりますが 、少なくとも 3 年程度の期間が必要と考えられます。
専従性
労務の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものである必要があります。
週に 1、2 回手伝っていた場合などは認められないことが多いです。
財産の維持又は増加との因果関係
特別の寄与行為の結果として被相続人の財産を維持又は増加させていることが必要です。
評価の方法
事案に応じて、以下のような評価の方法があります。
- 相続人が通常得られたであろう給付額から生活費相当額を控除し、それに寄与の期間を乗じて算出する
- 相続財産の形成に貢献したと思われる比率で算出する
これらによって算出した評価額を基礎として、更に一切の事情を考慮して最終的な額を定めます。
この点、以下のような裁判例があります。
<神戸家裁昭和50年5月31日>
相続開始当時の昭和47年度における全産業全女子労働者平均給与額…によると…年間給与の平均額は約70万円…であり、申立人美貴子の協力期間は23年であるから、その給与相当額は約1610万円であるところ、その約2分の1は生活費(食費30他20パーセント)としてすでに満足を得ているものと認めるし、また配偶者の法定相続分は家事労働とその他通常の協力を前提としたものであるから、被相続人が長く病臥していたなど特別事情のない本件では申立人美貴子の営業への協力分はさらにその2分の1を控除した額すなわち約400万円をもって遺産に対する同人の寄与分と認めるのが相当である。
<福岡家裁久留米支部平成4年9月28日>
信夫は、昭和46年ころから家業の薬局経営を手伝い、昭和56年からは秀次に代わって経営の中心となり、昭和60年に薬局を会社組織にした後も、店舗を新築するなどして経営規模を拡大した。その間、信夫が無報酬又はこれに近い状態で事業に従事したとはいえないが、それでも、信夫は、薬局経営のみが収入の途であった秀次の遺産の維持又は増加に特別の寄与貢献を相当程度したものと解せられる。
その程度は、本件における一切の事情を斟酌し、秀次の相続開始時における遺産の評価額の総額1億2943万6880円から当時の負債3715万1256円を控除した9228万5624円の32パーセント強、金額にして3000万円と認めるのが相当である。
<大阪高裁平成27年10月6日>
被相続人が目録記載A2ないし7の各土地をみかん畑として維持することができたのは、相手方Bが昭和55年ころから農業に従事していたことによるものであると推認される。
そして、同A2及び3の各土地は宅地見込地として評価されるが、当面はみかん畑としての利用が考えられ、これを売却するとしても市場参加者としては…市内の農業従事者が中心となると見込まれること、A4ないし7の各土地は山畑でありみかん畑以外の利用は考えにくいことからすれば、耕作放棄によりみかん畑が荒れた場合には取引価格も事実上低下するおそれがあるといえる。
したがって、相手方Bには、みかん畑を維持することにより遺産の価値の減少を防いだ寄与があるといえ、農業の収支が赤字であったことは上記判断を左右するものではない…。
そして、上記認定の相手方Bの農作業従事の程度に照らせば、上記寄与は特別の寄与であると認めることができる。
…以上をふまえ、相手方Bの寄与分については、目録記載A2ないし7の各土地の相続開始時の評価額の30パーセントとみるのが相当である。
療養看護型
病気療養中の被相続人の療養看護に従事した場合です。
療養看護の必要性
①療養看護を必要とする病状であったこと、②近親者による療養看護を必要としていたこと、の両方が必要です。
高齢というだけでは介護が必要な状態だったとはいえず、疾病などで療養や介護を要する状態であったことが前提になります。
入院・施設へ入所していた場合、その期間は原則として療養看護の必要性は認められません。
①療養看護を必要とする病状であったこと、②近親者による療養看護を必要としていたこと、があったといえるかどうかは要介護2以上の状態にあることが目安と考えられます。
要介護2とは、立ち上がりや歩行が自分でできないことが多く、食事・着替えは何とか自分でできても、排せつは一部手助けが必要となるような状態で、理解力の低下がみられることもあります。
被相続人の症状、要介護状態に関する資料としては、要介護認定通知書、要介護認定資料(認定調査票、かかりつけ医の意見書など)、診断書などがあります。
療養看護の内容に関する資料としては、介護サービス利用票、介護サービスのケアプラン、施設利用明細書、介護利用契約書などがあります。
①療養看護を必要とする病状であること、②近親者による療養看護を必要としていたことが要求されるため、そのような病状がない被相続人に対して家事援助をしても、寄与分は認められません。
特別な貢献
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献であることが必要です。
この点、以下のような裁判例があります。
<広島家裁呉支部平成22年10月5日>
相手方Eは、「相手方Eは、…に転居するまでの平成10年から平成17年までの間、頻繁に山梨から…に赴き、家事の手伝いをしたり、被相続人G及びHの介護をしたりした。これは寄与分として認められるべきである」旨主張する。
しかし、まず、平成10年からHが死亡する平成13年までについてみると、相手方Eは、居住地の山梨県から交通費をかけて…を訪ね、被相続人GやHの家事を手伝ったことは認められるけれども、その間、Hが入院する程の重篤な状態にあったわけではないことが認められ、被相続人Gの健康状態も比較的良好であったことからすれば、相手方Eのした家事の援助は寄与分が認められるほどの療養看護に当たるとはいえない。
…次に、平成13年から平成17年までについてみると、Hが死亡してから平成15年×月までは、被相続人Gは、相手方Fと生活し、家事をするなど元気な状態であった上、その後も相手方Eが…に転居してくるまでのほとんどの間、被相続人Gは、自立した生活をしていた。
この間、被相続人Gは、平成14年に2か月程度、平成15年×月に20日程度、入院生活を送ったが、その際、相手方Eは、「毎日病院に通って、差し入れなどをした。…に滞在中、自らの負担で、被相続人Gの夕食を作るなどした。」旨述べるが、これをそのまま信用することはできないし、一定の介護的な援助をしたことが認められるとしても、それは親族間の協力にとどまり、寄与分が認められるほどの療養看護とまで評価できるものではない。
…相手方Eは、被相続人Gの身上の世話をするため、多大な金銭的犠牲を払って…に転居した旨主張する。
確かに、相手方Eは、平成17年×月、被相続人G所有の土地…上に家屋を建て、これに家族共々居住するようになったことが認められる。
しかし、このこと自体は、遺産の維持、形成に寄与するものでなく、むしろ、上記土地を他人所有家屋が存在する土地に変化させたものであり、その限度では、遺産の財産的価値を減少させる行為といえる。
…相手方Eは、「被相続人Gは入院する1か月前まで車を運転し、毎日自分でスーパーに行って食材を買い、昼食は自分で作り、店にも出ていた。通院も自分でしていた。相手方Eは、朝と夕方被相続人G宅に行き、朝はパンを焼いたり簡単な朝食を作ったり、夜は夕食を差し入れたりしていた。時々は、被相続人Gが相手方E宅を訪ね一緒に食事をすることもあった。」旨述べている。
上記のような相手方Eの供述を前提としても、それは親族間の協力にとどまり、遺産の維持、形成に対する寄与には当たらない。
無償性
無報酬かそれに近い状態で療養看護をすることが必要です。
もっとも、 通常の介護報酬に比べて著しく少額であるような場合、無償と評価できることもあります。
これに対し、無報酬かそれに近い状態で療養看護をしていても、被相続人の資産や収入で生活していれば、無償と評価できないこともあります。
継続性
労務の提供が相当期間に及んでいることが必要です。
期間は一切の事情を考慮して個別に判断されることになりますが、少なくとも1年以上が必要であると考えられます。
専従性
療養看護が片手間ではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。
仕事をしながらの療養看護では、専従性が認められ難いと考えられます。
財産の維持又は増加との因果関係
療養看護により、職業看護人に支払うべき報酬などの看護費用の出費を免れたという結果が必要です。
評価の方法
介護報酬基準額に日数を乗じ、さらに裁量割合を乗じて算出するのが一般的な方法です。
裁量割合とは、介護報酬基準額は資格を有する者への報酬であり、扶養義務を負う親族と第三者とでは報酬額が変わることを考慮するための数値をいいます。
通常は、0.5~0.8(0.7が平均)とされています。
もっとも、相続財産の形成に貢献したと思われる比率で寄与分を算出する方法もあります。
この点、以下のような裁判例があります。
<大阪家裁平成19年2月8日>
平成14年2月ころから被相続人に認知症の症状が顕著に出るようになったため、相手方は、被相続人の3度の食事をいずれも相手方方でとらせるようになり、被相続人が…を訪問するときは、相手方が往復とも被相続人に付きそうようになった。
このころから、被相続人は常時、見守りが必要な状態となり、また、被相続人の排便への対応にも相手方は心を砕いていた。
申立人らも、平成14年以降の3年間については、相手方が被相続人の介護を献身的に行っていたことを認めており、この期間については、相手方の被相続人に対する身上監護には、特別の寄与があったものと認められる。
…相手方の被相続人に対する身上監護については、親族による介護であることを考慮し、1日当たり8000円程度と評価し、その3年分(1年を365日として)として、8000円×365日×3=876万円を寄与分として認めることとした。
<大阪家裁平成19年2月26日>
…上記の標準賃金を参考にしつつ、申立人Bの介護が⑴勤務としてではなく、あくまで親族介護であること、⑵少人数による在宅介護のため、完璧な介護状態を保つことは困難だったと窺われること、⑶申立人Bが他の親族より多額の小遣いを取得していたこと、⑷昼間は、他の親族も交代で被相続人の介護を手伝っていたこと、⑸被相続人の生活が次第に昼夜逆転し、深夜の排泄介助もしばしばあったことは負担感を増したといえること、⑹被相続人が…体型であり、介護の肉体的負担が極めて大きかったといえることなどを考慮して、1日当たりの介護費用を1万2000~1万3000円程度として算定することとする。
とすれば、申立人Bの当該期間の介護労働を金銭的に換算すると、600万円程度との評価が可能である。
…上記の数字は、専ら当該期間中の介護面のみを抽出して金銭換算したものであるが、最終的な寄与分評価としては、上記の数字を踏まえ、相続財産の額その他一切の事情を考慮(民法904条の2)し、相続人間の実質的衡平に資するべく評価を決定することとなる。
本件において、申立人Bは、⑴平成8年4月以来、被相続人の洗髪を介助するなど、軽度の身体介助は相当早期から始まっていたこと、⑵失禁の後始末など排泄にまつわる介助も平成8年ころから既に行っていたこと、⑶平成11年ころから、被相続人が幾度も転倒しており、その行動に注意を要する状態は既に始まっていたことなどを併せて考慮すれば、最終的な寄与分の評価としては、遺産総額中の3.2%強である750万円と認めることとする。
<大阪高裁平成19年12月6日>
被相続人は平成10年頃からは認知症の症状が重くなって排泄等の介助を受けるようになり、平成11年には要介護2、平成13年は要介護3の認定を受けたもので、その死亡まで自宅で被相続人を介護したCの負担は軽視できないものであること、Cの不動産関係の支出は、本件の遺産の形成や維持のために相応の貢献をしたものと評価できるけれども、本件建物の補修費関係の出費は、そこに居住するC自身も相応の利益を受けている上に、遺産に属する本件建物の評価額も後記のとおりで、その寄与を支出額に即して評価するのは、必ずしも適切でないこと、更に農業における寄与についても、Cが相続人間では最も農地の維持管理に貢献してきたことは否定できないが、公務員として稼働していたことと並行しての農業従事であったことをも考慮すると、専業として貢献した場合と同視することのできる寄与とまでは評価できないこと、Cは、もともと、親族として被相続人と相互扶助義務を負っており、また、被相続人と長年同居してきたことにより、相応の利益を受けてきた側面もあること等本件の諸事情を総合考慮すれば、Cの寄与分を遺産の30%とした原審判の判断は過大であって、その15%をもってCの寄与分と定めるのが相当というべきである。
そうすると、後記のとおり、本件遺産の評価額合計は、9360万3235円であるから、Cの寄与分は、その15%に当たる1404万0485円となる。
寄与分の期間
民法改正により、相続開始から10年が経過した後にする遺産分割には、原則として寄与分の規定は適用されないことになりました(改正後民法904条の3柱書本文)。
寄与分の規定が適用されないことは、具体的相続分による遺産分割を求める利益がなくなるという効果が生じることを意味します。
そのため、期間経過後に具体的相続分による分割を求める利益について不当利得返還請求などを認めることは想定されていません。
したがって、期間経過後には、法定相続分を前提に遺産分割を行うことになります。
もっとも、次のどちらかに該当すれば、相続開始から10年を経過した後でも、寄与分の規定が適用されます(改正後民法904条の3柱書但書)。
- 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
- 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、その相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
なお、「やむを得ない事由」とは、客観的な事情から、相続人に遺産分割の申立てをすることを期待することがおよそ期待できない場合をいい、容易には認められないものと考えられます。
改正後の民法は令和3年4月28日から2年以内に施行されることになっていましたが(改正民法附則1条本文)、「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和3年12月14日閣議決定)により、令和5年4月1日に施行されることになりました。
そして、寄与分の期間制限については、改正民法の施行日前に相続が開始した遺産分割にも遡及して適用されます。
具体的には、次のどちらかの遅い時までが寄与分の期限となります(改正民法附則3条)。
- 相続開始の時から10年を経過する時
- 改正民法施行の時から5年を経過する時