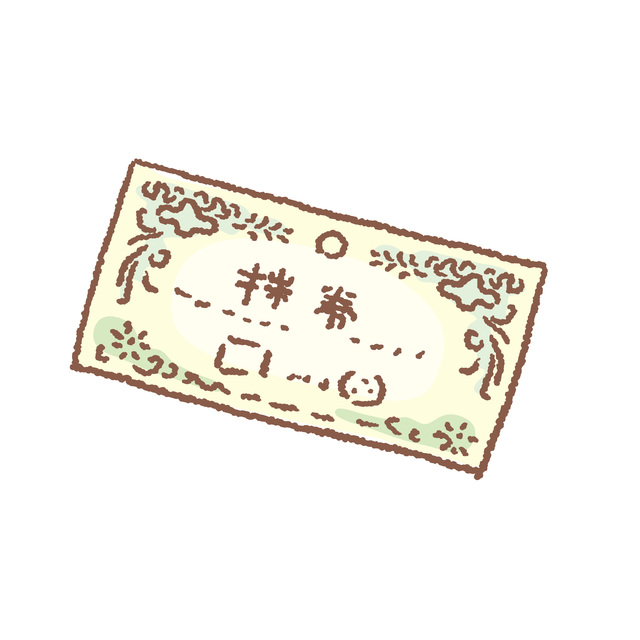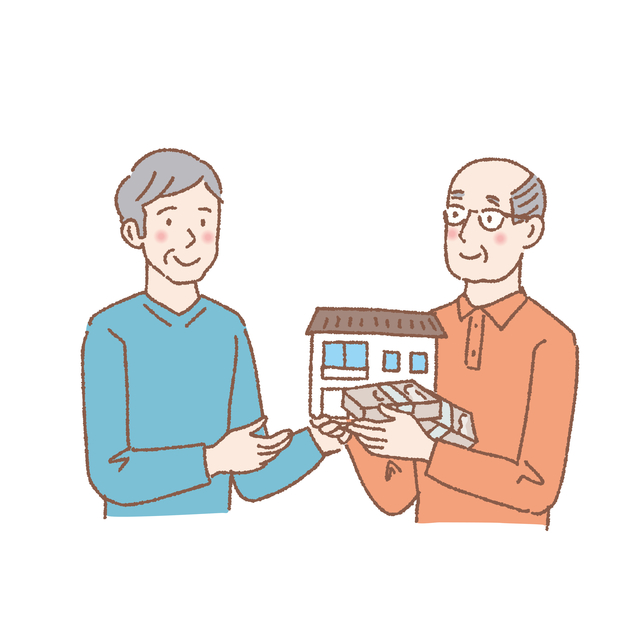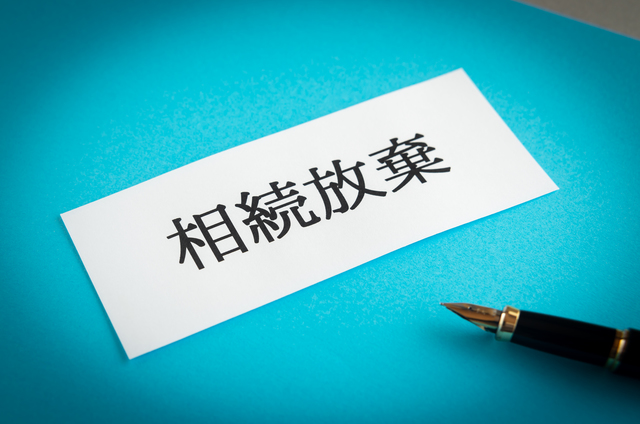
相続人は、相続放棄により、被相続人の財産のすべてを相続しないことができます。
被相続人に債務がある場合、相続放棄を検討することになりますが、相続放棄ができる期間には制限があるため注意が必要です。
また、特定の行為をすることにより相続放棄ができなくなることもあります。
以下、相続放棄のポイントについて説明します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続により被相続人の財産を包括的に承継するのを拒否することです。
相続放棄すると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことになります。
なお、お墓(位牌や仏壇なども)は相続財産ではないため、相続放棄の対象にはなりません。
相続放棄をすると、その相続人は、初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。
相続放棄の対象となる相続
次順位の相続人
被相続人が死亡し、第1順位の相続人である子が相続放棄した場合、第2順位の相続人である直系尊属が被相続人を相続することになります。
そこで、第1順位の相続人が相続放棄した場合、第2順位の相続人である直系尊属も相続放棄を検討する必要があります。
そして、第2順位の相続人である直系尊属も相続放棄した場合、第3順位の相続人である兄弟姉妹が被相続人を相続することになります。
そこで、第1順位・第2順位の相続人が相続放棄した場合、第3順位の相続人である兄弟姉妹も相続放棄を検討する必要があります。
なお、子が相続放棄すると、孫も相続人にならないことが確定するため、被相続人の孫は相続放棄を検討する必要はありません。
また、兄弟姉妹が相続放棄すると、甥・姪も相続人にならないことが確定するため、被相続人の甥・姪は相続放棄を検討する必要はありません。
代襲相続人
Aの子Bが死亡し、Bの子CがBの相続を放棄した後、Aが死亡した場合、Aの孫であるCはAの代襲相続人となります(民法887条2項)。
この場合、CはBの相続を放棄していても、Aの財産を相続することもできるため、改めて相続放棄を検討する必要があります。
再転相続人
Aが死亡した後、Aの子Bも死亡し、Bの子CがBの相続人となるような場合を再転相続、Cを再転相続人といいます。
Cは、Bの相続人であり、かつ、Aの相続人でもあり、2つの立場をもっています。
再転相続人が相続を放棄できるかどうかは、次のようになります(最高裁昭和63年6月21日参照)。
- CがBの相続を承認した後、CがAの相続人であることを知った場合、CはAの相続を放棄できます。
- CがBの相続を放棄した場合、CはAの相続人であるBの立場を失うので、Aの相続を承認できません。
- CがAの相続を放棄した後、Bの相続を承認できます。
<最高裁昭和63年6月21日>
CがBの相続を放棄して、もはやBの権利義務をなんら承継しなくなった場合には、Cは、右の放棄によってBが有していたAの相続についての承認または放棄の選択権を失うことになるのであるから、もはやAの相続につき承認または放棄をすることはできないといわざるをえない
…CがBの相続につき放棄をしていないときは、Aの相続につき放棄をすることができ、かつ、Aの相続につき放棄をしても、それによってはBの相続につき承認または放棄をするのになんら障害にならず、また、その後にCがBの相続につき放棄をしても、Cが先に再転相続人たる地位に基づいてAの相続につきした放棄の効力がさかのぼって無効になることはない…。
相続放棄の方法
家庭裁判所に対して相続放棄の申述をします(民法915条1項)。
相続放棄の申述をするには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書を提出します。
相続放棄の申述書には、次の書類も添付します。
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(相続放棄する相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
その他、被相続人との関係に応じてこれら以外の戸籍も必要となります。
相続放棄の期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をする必要があります(民法915条1項本文)。
この期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に進行します(最高裁昭和51年7月1日)。
相続人は、相続の放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます(民法915条2項)。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」がいつなのか問題となった裁判例を紹介します。
相続財産がないと考えいていた場合
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続開始の原因となる事実とこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時です。
もっとも、相続人が相続開始の原因となる事実とこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったのが、①相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、②このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続人が相続財産の全部か一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時となります(最高裁昭和59年4月27日)。
<最高裁昭和59年4月27日>
民法915条1項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて3か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合には、通常、右各事実を知った時から3か月以内に、調査すること等によって、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがって単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
再転相続の場合
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合、相続放棄できる期間は、死亡した相続人の相続人(再転相続人)が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月となります(民法916条)。
そして、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法916条)とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人(再転相続人)が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいいます(最高裁令和元年8月9日)。
例えば、Aが死亡した1か月後、Aの子Bが相続放棄しないで死亡し、Bの子CがBの相続人となる場合、CはBが死亡して自らが相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄ができます。
<最高裁令和元年8月9日>
民法916条の趣旨は、BがAからの相続について承認又は放棄をしないで死亡したときには、BからAの相続人としての地位を承継したCにおいて、Aからの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することになるという点に鑑みて、Cの認識に基づき、Aからの相続に係るCの熟慮期間の起算点を定めることによって、Cに対し、Aからの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障することにあるというべきである。
再転相続人であるCは、自己のためにBからの相続が開始したことを知ったからといって、当然にBがAの相続人であったことを知り得るわけではない。
また、Cは、Bからの相続により、Aからの相続について承認又は放棄を選択し得るBの地位を承継してはいるものの、C自身において、BがAの相続人であったことを知らなければ、Aからの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできない。
Cが、BからAの相続人としての地位を承継したことを知らないにもかかわらず、CのためにBからの相続が開始したことを知ったことをもって、Aからの相続に係る熟慮期間が起算されるとすることは、Cに対し、Aからの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障する民法916条の趣旨に反する。
以上によれば、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいう…。
なお、Aからの相続に係るCの熟慮期間の起算点について、Bにおいて自己がAの相続人であることを知っていたか否かにかかわらず民法916条が適用されることは、同条がその適用がある場面につき、「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき」とのみ規定していること及び同条の前記趣旨から明らかである。
期間の伸長
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、放棄をする必要がありますが(民法915条1項本文)、3か月という期間は伸長することもできます(民法915条1項但書)。
ただ、相続放棄をすべき期間の伸長についても、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の期間伸長の申述をする必要があります。
相続放棄の期間伸長の申述をすると、家庭裁判所は、相続放棄の期間を3か月延長することが通常です。
相続放棄できない場合
次の場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄できません(民法921条)。
- 相続財産の全部又は一部を処分した場合(1号)
ただし、保存行為・一定の期間を超えない賃貸(民法602条)は除きます - 相続放棄をできる期間内に限定承認・相続放棄をしなかった場合(2号)
- 限定承認・相続の放棄をした後でも、①相続財産を隠匿、②私に消費、③悪意で相続財産の目録中に記載しなかった場合(3号)
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は除きます
単純承認とは、被相続人の権利・義務を無限に承継することです(民法920条)。
単純承認の詳細については、こちらのページで説明します。
相続人全員が相続放棄した場合
相続人全員が相続放棄すると、相続財産の所有者がいないことになります。
そこで、相続財産を管理・清算する必要があれば、相続財産の清算人を選任して(民法952条1項)、相続財産の管理人が不動産の売却や預貯金の解約などして債務の支払いをし、財産や債務を消滅させることになります。
相続財産の管理人がすべての債務の支払いをし、特別縁故者に分与(民法958条の3)した後に財産が残れば、最終的には国庫に帰属します(民法959条)。
相続財産管理人を選任するには、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをします。
相続放棄をした者の義務
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合、相続人又は相続財産の清算人(民法952条1項)に対して財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないとされています(民法940条1項)。
したがって、①相続の放棄をした者が負う義務の内容は、現に占有している財産の保存義務にとどまり、管理義務までは負わず、②相続の放棄をした者が財産を保存する義務を負うのは、相続財産に属する財産を厳に占有している場合に限られ、③相続の放棄をした者の義務は、相続人や相続財産の清算人に対して財産を引き渡すことで終了します。