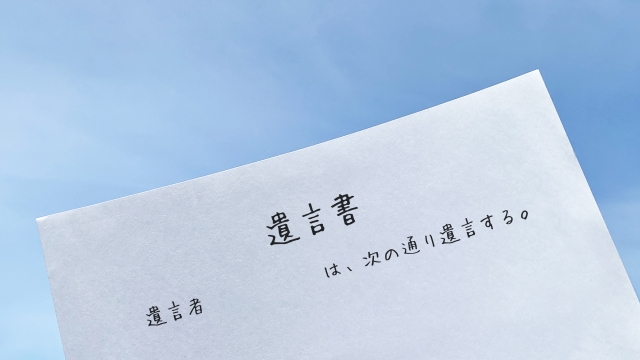自筆証書遺言は、家庭裁判所において開封・検認を行う必要があります。
以下、遺言書の開封・検認の手続き等について説明します。
遺言書の開封
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することはできません(民法1004条3項)。
「封印のある遺言書」とは、封に押印のある遺言書を意味し、単に封入された遺言書は含まれません。
遺言書の開封は遺言書の検認の一環として検認期日に行うため、特別に開封の申立てを必要としません。
自筆証書遺言は、封筒などに封入することは必要ありませんが、封がされていた遺言書の封を開封すると、遺言の改変を疑われるおそれがあります。
また、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封すると、過料の制裁があります(民法1005条)。
遺言書の検認
検認の意味
検認は、遺言書の成立と存在を確認するとともに、遺言書の偽造・変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するための手続です(民法1004 条1項)。
検認によって遺言書の現状が確定するため、検認後に遺言書原本が滅失・紛失しても、検認調書によって遺言執行ができます。
検認は、遺言が遺言者の真意に基づくか等、遺言が有効かどうかを判断する手続きではありません。
そのため、検認をしたからといって、遺言書が真正に成立したとの推定はされず(東京高裁昭和32年11月15日)、検認を経た遺言書の効力を裁判で争うこともできます(大審院大正7年4月18日)。
また、検認をしなくても遺言の効力には影響がなく、検認を経ないでした遺言執行も無効ではありません。
もっとも、実務上、不動産の所有権移転登記や預貯金の名義変更・解約等にあたり、自筆証書遺言の検認を経ていることが必要となります。
そのため、不動産の登記や預貯金の名義変更等にあたっては、検認をすることが事実上の条件となっています。
検認の対象となる遺言
公正証書遺言以外の方式によって作成された遺言が検認の対象となります(民法 1004条2項 )。
もっとも、令和2年7月10日に施行された遺言書保管法に基づき、法務局に保管されている自筆証書遣言は検認の対象となりません(遺言書保管法11条) 。
検認の申立て
検認の申立てをするのは、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人です(民法1004条1項)。
そのため、遺言執行者は、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人に当たらない場合、検認を申立てることはできません。
検認の申立てにあたっては、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされていますが(民法1004条1項前段)、実務上、遺言書は検認期日において申立人が持参して提出すれば足り、申立時に遺言書を提出する必要はないのが一般です。
また、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遅滞なく検認を申立てなければなりません(民法1004条1項)。
遺言書の隠匿をした場合、相続する権利がなくなります(民法891条5号・965条)。
なお、遺言書の提出を怠ったり、検認を経ないで遺言を執行した場合、過料の制裁があります(民法1005条) 。
検認の申立ては、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません(家事事件手続法212条)。
検認の手続
検認の申立てがあると、家庭裁判所は、申立人・相続人に対して検認の期日を通知します。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各自の判断に委ねられており、検認期日に相続人等の関係者全員が立ち会うことができなくても、検認は行われます。
検認期日において、封印されている遺言書であれば、立ち会った関係者の前で開封します。
そして、裁判官が、遺言書を発見した状況や保管していた状況、遺言書の文字が本人の文字か、押してある印影が本人の印によるものかを質問します。
質問に対しては自身の記憶に従って答えればよく、わからなければわからないと答えれば差し支えありません。
そして、家庭裁判所は、遺言の方式に関する事実の調査の結果等を記載した検認調書を作成します(家事事件手続法211条)。
検認調書には、遺言書の写しが末尾に添付されます。
検認終了後、裁判所書記官は、検認済証明書を作成し、これを遺言書原本の末尾に編綴、契印して、遺言書原本を提出者に返還します。