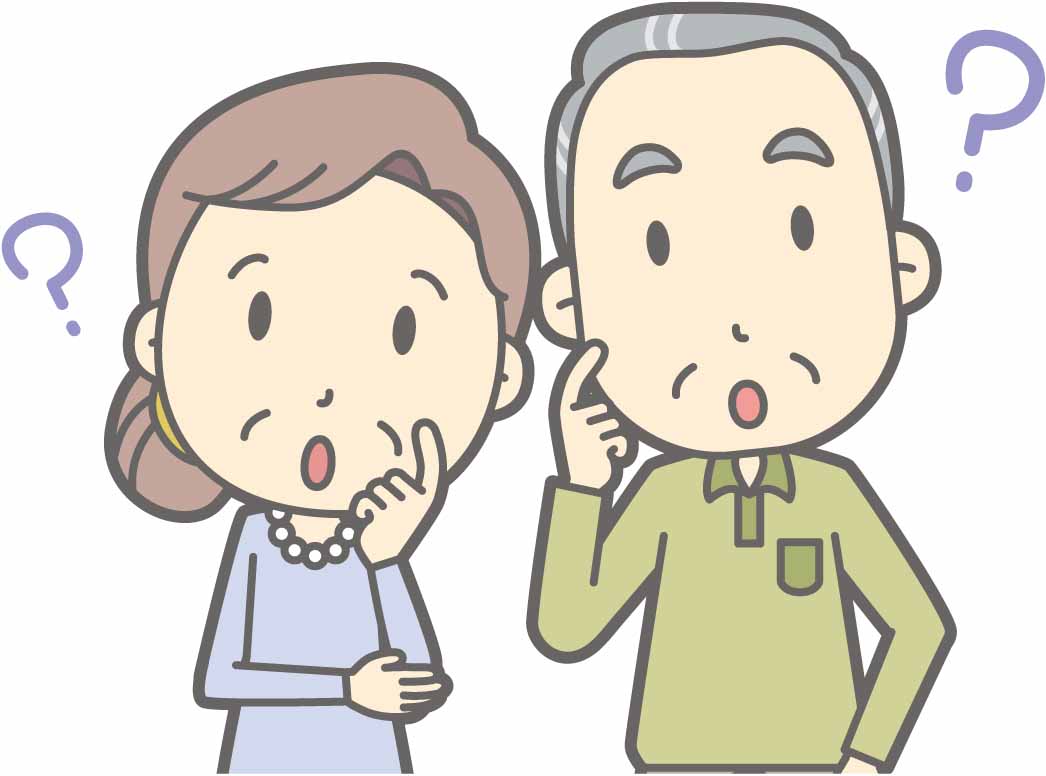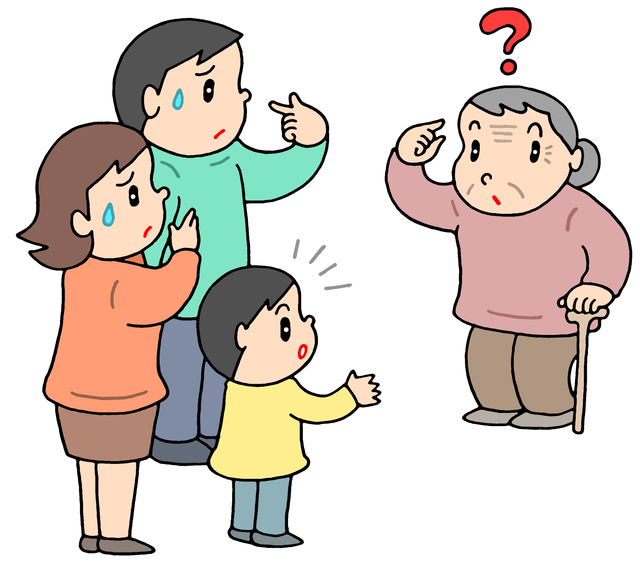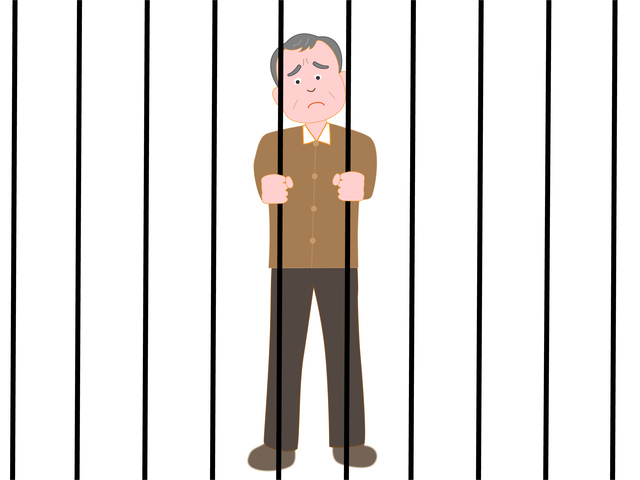
高齢者の囲い込みとは、高齢の親のいる子供などが、親と他の子供や親族を会わせないようにする問題のことをいいます。
子供が将来の相続を見越して、自分に有利な遺言を作成させたり、親の預貯金を使い込んでしまい、後に使途不明金が問題となることもあります。
高齢者の囲い込みの問題に対応するには、次のような方法が考えられます。
- 成年後見制度の利用
- 面会の妨害を禁止する仮処分
- 損害賠償請求
成年後見制度の利用
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。
判断能力が不十分な方を保護して、適切な財産管理を行うための制度です。
高齢者を囲い込むことで適切な財産管理がなされていないことが疑われる事案においては、有効な方法となることがあります。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がありますが、成年後見制度を利用するためには、後見開始、保佐開始、補助開始の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
申立てがあると、家庭裁判所は、申立人、後見人などの候補者、本人から事情を聴取したり、本人の親族の意見を照会します。
そのような過程において、囲い込まれている本人の状況がわかったり、本人の財産を管理する成年後見人などが選任されることで、本人の財産の適切な管理が図られるとともに、本人との面会のきっかけがつかめることもあります。
成年後見制度についてはこちらのページもご覧ください。
面会の妨害を禁止する仮処分
アルツハイマー型認知症と診断された両親を、長男(兄)が福岡県の自宅から連れ出して横浜市内の老人ホームに入所させ、長女(妹)と両親との面会を妨害している事案について、長女と両親との面会の妨害を禁止する仮処分決定を認可した裁判例があります(横浜地裁平成30年7月20日)。
この裁判例は、子供の両親に面会する権利を認めた初めての裁判例とされています。
もっとも、面会の妨害が禁止されるとしても、具体的にどのように面会を実現すればよいのかについてまでは明らかではありません。
<横浜地裁平成30年7月20日>
本件は、債権者[長女(妹)]が、債権者及び債務者[長男(兄)]の父であるA及び同母であるB(以下「A」及び「B」を合わせて「両親」という。)が入居している老人ホーム及び債務者が債権者と両親との面会を妨害していると主張し、人格権を被保全権利として、債務者及び同老人ホームを経営する会社は債権者が両親と面会することを妨害してはならないとの仮処分命令を申し立てたところ、横浜地方裁判所が、債務者及び前記会社のため各金2万円の担保を立てさせて認容する旨の決定をしたことから、債務者がこれを不服として保全異議を申し立てた事案である。
…被保全権利の存否について
債権者は、両親の子であるところ、…両親はいずれも高齢で要介護状態にあり、アルツハイマー型認知症を患っていることからすると、子が両親の状況を確認し、必要な扶養をするために、面会交流を希望することは当然であって、それが両親の意思に明確に反し両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り、債権者は両親に面会をする権利を有するものといえる。
そして、…債権者が両親と面会することが両親の権利を不当に侵害するような事情は認められないことから、本件被保全権利は一応認められる。
…保全の必要性について
…両親が現在入居している施設に入居するに当たり債務者が関与していること、債務者が債権者に両親に入居している施設名を明らかにしないための措置をとったこと、債権者が両親との面会に関連して、家庭裁判所に親族間の紛争調整調停を申し立てる方法をとってもなお、債務者は家庭裁判所調査官に対しても両親の所在を明らかにせず、調停への出頭を拒否したこと、本件審尋期日においても、債務者は、債権者と両親が面会することについて協力しない旨の意思を示したことが認められる。
これらの事情を総合すると、債務者の意向が両親の入居している施設等の行為に影響し、債権者が現在両親に面会できない状態にあるものといえる。
また、債務者の従前からの態度を考慮すると、上記の状況が改善する可能性は乏しいものといえ、今後も、債務者の妨害行為により債権者の面会交流する権利が侵害されるおそれがあるものといえる。
なお、債務者は、両親の意向を尊重しているだけで、債務者が債権者と両親との面会を妨害している事実はないなどと主張するが、…債務者の行為が、債権者が両親と面会できない状況の作出に影響していることは否定できない。
以上によると、債権者が両親に面会することにつき、債務者の妨害を予防することが必要であることから、本件保全の必要性も認められる。
損害賠償請求
80代の母親を自宅から連れ出した長女と二女が、三女と母親が会うことを阻み続けた事案において、長女と二女の行為が不法行為に当たるとし、長女と二女に連帯して慰謝料110万円の支払い命じた裁判例があります(東京地裁令和元年11月22日)。
この裁判例は、子を両親に会わせないことが不法行為になることを明確にしたものですが、損害賠償請求は事後的に精神的苦痛の慰謝を図るものであり、直接の面会が命じられたわけではなく、両親との面会を実現する方法については課題が残ります。
<東京地裁令和元年11月22日>
本件は、原告[三女]が、被告ら[長女と二女]が原告と母との面会を妨害するところ、同妨害が母と会いたいという原告の法的な保護に値する利益を侵害し、社会的相当性を逸脱するものであると主張して、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金…の連帯支払を求める事案である。
2 争点⑴(被告らが原告とAとの面会をさせないことが、親に会いたいという子である原告の法的な保護に値する利益を侵害し、社会的相当性を逸脱するものか。)について
⑴ …Aが、独力で、公共交通機関を利用するなどし、移動をすることができない状況である以上、原告は、被告らによるAとの面会拒絶等により、Aと面会をし、交流をするという機会を奪われる状況に置かれているということができる。
そして、たとえ子が成人に達した後であっても、子が親を思い、親と面会をし、交流をしたいと願うことは、子の自然な思いとして、我が国の法秩序においても尊重すべきものであり、また、親が会いたくないという意向を有しているといった事情でもない限り、親と面会をし、交流をすることは、本来自由にされるべきものと考えられる。
そうすると、親と面会をし、交流をしたいという子としての素朴な感情、又は自由に親と面会をし、交流をするという利益は、それ自体が法的な保護に値するということができる…から、合理的な理由もないのに、親と会って交流をするという子の機会を奪い、同感情等をいたずらに侵害することは、社会的相当性を逸脱するものとして、不法行為を構成するものと解すべきである。
⑵ そこで、被告らによる原告とAとの面会拒絶等について、合理的な理由がないものであるか否かを検討する。
ア まず、…Aにおいて、原告と会いたくないという意向を有しているという事実を認めることはできない。
イ …Aは、…小脳梗塞をいったん発症した以上、一定のストレスにより小脳梗塞の再発をするリスクがあるということ自体を否定することはできないが、当該リスクを理由として原告とAとの面会等を拒絶することは、不合理なものといわざるを得ない。
また、万が一にもAが小脳梗塞を再発し、取り返しのつかない事態を招くわけにはいかないという理由が、原告とAとの面会等を拒絶する理由として不合理なものである以上、Aをそっとしておいてあげるのが相当であるという判断についても根拠が乏しいといわざるを得ないから、同判断がAの身上看護を考えてのものであったとしても、そのような判断が原告とAとの面会等を拒絶する合理的な理由となり得るものではない。
⑶ …被告らそれぞれがAの任意後見人として、Aの身上看護について責務を負うほか、その職務の遂行に当たって一定の裁量を有していることを考慮しても、平成24年11月29日以降の長期にわたり、被告らが原告とAとの面会を拒絶等していることは、合理的な理由もないのに、親と会って交流をするという機会を原告から奪い、親と面会をし、交流をしたいという法的な保護に値する子としての原告の感情等をいたずらに侵害するものであるから、不法行為を構成するといわざるを得ない。
⑷ なお、被告らは、補助参加人に対し、任意後見人[被告らを任意後見人とする任意後見について任意後見監督人として選任された弁護士]としての職務内容(Aの所在及び利用施設を含む。)を報告し、補助参加人は東京家庭裁判所に対し、報告書類を提出しているが、…同裁判所又は調停の担当裁判官から問題点を指摘されないことが、被告らによる面会拒絶等が違法であるとはいえないことを直ちに意味するものではない。
また、その点をひとまず措くとしても、…補助参加人は、Aと会ったことはなく、Aから原告と会うことについての意向を聴取するなどしたことはないし、Aの病状について、医師から説明を受けたこともないことが認められるから、同裁判所又は調停の担当裁判官が的確な判断をするだけの情報を得ていたとは考えられない。
そうすると、同裁判所から、又は調停の担当裁判官から問題点を指摘されなかったからといって、前記⑴から⑶までの判断が左右されるものではない。
3 争点(2)(原告の損害)について
⑴ 慰謝料額
…被告らが原告に対し、母の居所に関する情報を伝えることもないまま、Aとの面会を長期にわたり拒絶等していることは、不法行為を構成するところ、同不法行為の違法性の程度、その結果として原告が令和元年中に90歳を迎える高齢の母と面会をし、交流を図ることが長期にわたりできておらず、その間にAの認知症が進行している様子であること…、一方で、被告らにとっても、遠くから眺めるという方法であるとはいえ、原告のAとの面会の要望に応じ、その結果として調停が成立した…ことから、原告から更なるAとの面会の要求がされることがないのではないかと期待した期間もあったと考えられること等の本件に現れた一切の事情を考慮すると、原告の被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料額は、これを100万円とすることが相当である。
⑵ 弁護士費用相当損害金額
…被告らの不法行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料額は100万円とすることが相当であるところ、同慰謝料額に加え、本件事案の内容等の事情を考慮すると、被告らの不法行為と相当因果関係があると認められる弁護士費用相当損害金は、これを10万円とすることが相当である。